
|
モーリタニア・イスラム共和国
Islamic Republic of Mauritania
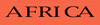
|
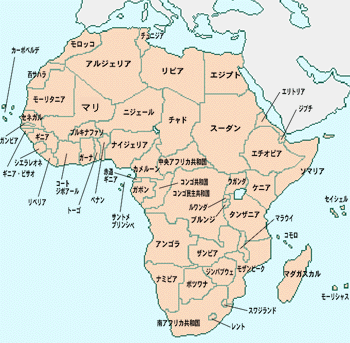
■地勢
アフリカ大陸の西側に位置するモーリタニアは、おおむね平坦で日本の約3倍の国土面積を持つ。全土がサハラ砂漠に位置するため、国土の90%以上が砂漠であり、中央部にリシャット構造と呼ばれる同心円状の特徴的な地形がある。
世界遺産にもなっているシンゲッティ、ウワダン、ウワラタ、ティシットの隊商都市は、ガーナ王国と並行して発展し、ガーナが滅亡した11〜12世紀にも繁栄を続けた。シンゲッティは、モーリタニア北西部に位置し、古くからシンゲッティ王国の首都であったが、12世紀頃になるとメッカの巡礼地の出発点となり、イスラム学者、学生、修道士などが集まる文化都市となった。
■西サハラ
Sahara Occidental)は、アフリカ大陸北西部の大西洋岸にある地域で、北から時計回りにモロッコ、アルジェリア、モーリタニアに接している。アフリカ分割においては、ギニア湾岸を除く西アフリカのほとんどの地域が東西5000km、南北4000kmにも及ぶ広大なフランスの植民地(フランス領西アフリカ)となった中で、西サハラとモロッコ最南部はフランス領に囲まれた島状の形でスペイン領として残った。
■サハラ砂漠
はアフリカ大陸北部にある世界最大の砂漠。東西5600km、南北1700kmで面積は約1000万km2であり、アフリカ大陸の3分の1近くを占める。サハラ砂漠全体の人口は約2500万人であり、そのほとんどはモーリタニア、モロッコ、アルジェリアに住む。サハラ砂漠内で最大の都市は、モーリタニアの首都ヌアクショットである。その他、重要な都市としては、タマンラセト、トンブクトゥ、アガデズ、ニアメ、ンジャメナが挙げられる。
■カナリア海流
Canary Currentは北大西洋海流の南側の分流で、アゾレス諸島とイベリア半島の間を南方向へ流れる寒流。一部はアフリカ海岸沿いにギニア海流へとつながっている。海流としてはごく弱いものであるが、流量は毎秒1500万トンほどである。またアフリカ北西の東赤道大西洋は、カナリア海流による離岸流の影響で湧昇流が発達する。
■ハルマッタン
(Harmattan)は、西アフリカで吹く貿易風である。熱風ではないが、きわめて乾燥しており湿気を奪う。また大量の0.5 - 10マイクロメートルのきわめて細かい砂塵を含んでおり、その砂塵は遠く北アメリカ大陸まで届く。
■セネガル川
アフリカ西部を流れる河川である。流域はギニア、マリ、モーリタニア、セネガルにおよぶ代表的な国際河川である。ギニア北部に源を発し北東に流れ、マリに入ると北西に転じ、セネガルとモーリタニアの国境を流れ、サンルイ州の州都サンルイで大西洋に注ぐ。河口付近の三角州には世界遺産に登録されているサン=ルイ島がある。
■砂漠化
植生に覆われた土地が不毛地になっていく現象をいう。ここでいう砂漠は「植物の生育や農業に適さない土地」といった意味が強く、乾燥した地域を意味する砂漠気候の「砂漠」とは意味にずれがある。もっとも、植生を失った土地が植物の蒸散作用を失うことで結果として乾燥した気候に傾いたメソポタミアのような例もある。
■アフリカ
Africa)は、広義にはアフリカ大陸およびその周辺のマダガスカル島などの島嶼・海域を含む地域の総称で、六大州の一つ。理的には地中海を挟んでヨーロッパの南に位置する。 赤道を挟んで南北双方に広い面積を持つ唯一の大陸でもあり、それに伴って多様な気候領域がある。
■アラブ世界
アラビア語を話す人々であるアラブ人が主に住む地域。現代政治的にはアラブ連盟の加盟諸国とみなされることが多く、アラブ諸国(en:Arab states)とも言う。ただし、アラブ連盟加盟国の中には、ジブチ・ソマリアなどアラブ人が少数派を占めるにすぎない国もある。
■フランス領西アフリカ
French West Africa、1895年、現在のセネガル、マリ、ギニア、コートジボワールに相当する地域に成立した。その後、フランスの植民地拡大にともない版図を拡大させた。1910年に現在の中央アフリカ共和国にあたるウバンギ・シャリ植民地を、1920年にチャドをフランス領赤道アフリカに変更した。1958年、ド・ゴール政権下でフランス共同体が発足したことに伴い解体した。
■歴史
8世紀(4世紀との説もある)ころから、国土の南東部に残されたクンビ=サレーを首都として、ガーナ王国が繁栄した。ガーナ王国は、セネガル川上流のバンブク周辺から産出される金とサハラ砂漠の岩塩から採取される塩、北方からの銅製品や衣服、装身具などの各種手工業製品の交易路を押さえ、その中継貿易の利で繁栄した。ガーナ王国滅亡後、500年以上にわたってベルベル人の支配が続き、黒人からなる地元勢力が抵抗したが、打倒にはいたらなかった。20世紀初めにフランスによって植民地化され、フランス領西アフリカの一部となった。1958年にフランス共同体が発足すると、共同体内の一共和国となった。1960年、アフリカ諸国の独立が進むなかで、11月28日に独立した。
■マウレタニア
マウレタニアは古代の北アフリカの地中海沿岸に独立したベルベル人のマウリ部族の王国。西アルジェリア、北モロッコ、ジブラルタルを含む広大な地域を支配。その後はローマ帝国の支配下に入って、王国の歴史は閉じることとなる。この国に因み、ムーア人の呼称が生まれ、ムーア人が支配するモーリタニアはマウレタニアの後継を称して国号が付けられたが、ムーア人支配層以外には民族的な繋がりがなく、地理的には何の関係もない。
■ガーナ王国
(Ghana) 、もしくはガーナ帝国は、8世紀(4世紀頃とも)から11世紀(13世紀とも)にかけて、サハラ越えの金と岩塩の隊商貿易の中継地として繁栄した黒人王国である。金や岩塩のほかにも、銅製品・馬・刀剣・衣服・装身具などの各種手工業製品の交易路を押さえ、その中継貿易の利で繁栄した。
■マリ帝国
1230年年代 - 1645年は、現在のマリ共和国周辺の領域で栄えたマンディンカ族の国家。歴代の王は早くからイスラム教を受け入れていたとされる。首都はニジェール川最上流部のニアニという説がある。
■国民
国民の40%がムーア人(アラブ人とベルベル人の混血)と黒人の混血、あとの30%ずつがムーア人と黒人である。黒人諸民族は、人口の7%を占めるウォロフ人のほか、トゥクロール人、サラホレ人、プル人などが居住する。多年のムーア人支配の影響で、社会の上層部はムーア人が占める。アラブ人には遊牧生活を営むベドウィンも存在する。
■セレール族
セネガル共和国で2番目に多い民族であり、ガンビア、モーリタニアにも居住する。 スーダン系で、主として中西部シン・サルーム地方で農業や漁業に従事している。セレール族は森羅万象にローグ(原義は『空』を意味する) と呼ばれる神を信じ、伝統的に熱心な宗教行事を生活のあらゆる場面で行ってきた。セレール族は他の民族と比較して外国からの宗教に抵抗した民族であり、イスラム化が最も遅かった民族である。
■ウォロフ族
ウォロフ族はセネガル、ガンビア、モーリタニアに居住する西スーダン系の民族。ウォロフ族は元来定住農耕民族である。セネガルでは、総全人口の約40%の多数を占め、また、北部サンルイ、中部カオラック、西部ダカールにおいても多数派である。しかし、カザマンス地方ではジョラ族が支配的でウォロフ族は少ない。
■トゥクロール族
セネガル川中流を起源とし、セネガルでは人口の約10%を占め、ダカールからマタム、バケルにかけての地方に分布し、農業、牧畜、漁業を兼業している。 さらに、現代セネガルでは商人の民族として知られ、国内で活発に商店を営んでいる一方、ヨーロッパなどに出稼ぎの親類を持ち、流通ネットワークを確立している。
■フラニ族
北西はモーリタニアから東はカメルーンまで西アフリカの多くの国に分布する民族。居住地域は主にサヘル地帯に広がっている。現在でも牧畜を営む人が多い。バントゥーともベルベル人やアラブ人とも異なる。独特の言語体系を有し、豊富な民話を継承している。
■ベルベル人
北アフリカ(マグレブ)の広い地域に古くから住み、アフロ・アジア語族のベルベル諸語を母語とする人々の総称。北アフリカ諸国でアラブ人が多数を占めるようになった現在も一定の人口をもち、文化的な独自性を維持する先住民族である。形質的にはコーカソイドで、宗教はイスラム教を信じる。
■ムーア人
Moorsは、北西アフリカのイスラム教教徒の呼称。主にベルベル人を指して用いられる。ローマ時代に北西アフリカの住民(ベルベル人)をマウハリムと呼んだことに由来する。マウハリムはフェニキア人の言葉で「西国の人」を意味する。7世紀以降には北アフリカのイスラム化が進み、イベリア半島に定着したアラブ人やベルベル人は原住民からモロと呼ばれるようになる。次第にモロはアラブ、ベルベルを問わずイスラム教徒一般を指す呼称となり、レコンキスタ以降は再び北西アフリカの異教徒住民を指すようなる。
■言語
アラビア語を公用語とする。(なお、モーリタニアで話されているアラビア語は「ハッサニア」と呼ばれ、黒人言語やベルベル語、フランス語の影響を受けている。)支配層のムーア人は人種的にはベルベル人の要素が強いが、文化的には長い間のイスラームの影響によりアラブ化しており、ベルベル語を保っているものは少数である。その他、ウォロフ語、フランス語などが使われている。高等教育を受けた、商業関係者、政府役人、教育関係者の間では多くフランス語が用いられる。
■アラビア語
アフロ・アジア語のセム語派に属する言語の一つ。主に西アジアや北アフリカのアラブ諸国で話されている。世界で3番目に多くの国と地域で使用されている言語であり、アラビア半島やその周辺、サハラ砂漠以北のアフリカ北部の領域を中心に(非独立地域を含めて)27か国で公用語とされており、また、国連の公用語においては、後から追加された唯一の言語でもある。
■ベルベル語
ベルベル語は現在主にモロッコ、アルジェリアで話されているアフロ・アジア語族の言語である。正確にはベルベル語派乃至ベルベル諸語と呼ぶべき物で、少しずつ異なる同系統の言語の総称であり、大きく分けて、タリフィート、タマズィグト、タシュリヒートの三つの方言がある。タリフィートは北モロッコ、タマズィグトは中央モロッコ、タシュリヒートはアルジェリアで話される。
■サハラ交易
Trans-Saharan tradeは、地中海沿岸諸国と西アフリカのあいだの交易で、先史時代から存在したが、最盛期は8世紀より16世紀後期に亘る。キャラヴァン・ルート (隊商路) の位置と交易量の盛衰を問う前に、このような交易がそもそもどのような形で存在したのかを考えることが重要である。
■ムワッヒド朝
ベルベル人のイスラム改革運動を基盤として建設されたイスラム王朝(1130年 - 1269年)。首都はマラケシュ。ムワッヒド朝の起源は、ベルベル人のマスムーダ族出身のイブン=トゥーマルトが開始したイスラム改革運動にある。彼は現在のモロッコ南部、アトラス山脈の出身で、12世紀の初頭に東方への遊学とマッカ(メッカ)巡礼に出た。
■ムラービト朝
1056年に北アフリカのサハラ砂漠西部に興ったベルベル系の砂漠の遊牧民サンハージャ族を母胎とするモロッコとアルジェリア北西部、イベリア半島南部のアンダルシアを支配したイスラム王朝。
<世界遺産>
■アルガン礁国立公園
モーリタニア西岸の国立公園。ティミリス岬を中心とする12000km2の国立公園で、面積のおよそ半分は海域である。沖合いには暖流と寒流がぶつかる潮目があるため、魚が多く集まり、それを目当てとする鳥類や海棲哺乳類も多く集まる。とりわけ、公園内のティドラ島、ニルミ島、ナイル島、キジ島、アルガン島などを含む砂州は、渡り鳥の楽園と化している。こうした鳥類と海洋生物の多彩さが評価され、ユネスコの世界遺産に登録されている。
公園内には500人ほどの先住民族イムラゲン人が住んでいるが、彼らはイルカの習性をうまく利用した伝統的なボラ漁を営んでいる。ボラ漁は適正なものだが、公園指定地域のすぐ外では乱獲が行われ、水産資源の悪化が懸念されている。
■ウワダニ、シンゲッティー、ティシットとウアラタの古代集落
クスール(単数形はクサール)は、中世にキャラバンが立ち寄った交易地に形成された独特の集落で、登録対象となった4つの町は、その古い街並みがよく保存されていることが評価された。これらの町はサハラ交易の拠点として栄えた歴史を持ち、またシンゲッティはモーリタニアをはじめとする西アフリカのイスラーム文化の中心地としても栄えた町で、地元ではイスラームの第七の聖地として巡礼の対象にもなっていた。町が持つこうした歴史的な重要性ももちろん評価されている。
■経済
独立以前は牧畜や南部の農業等しか産業が存在しなかった。1960年の独立以降、天然資源(鉱業、農業、漁業、牧畜)の開発と有効利用を中心に経済・社会の発展が図られ、特に漁業と鉱業の発展は著しかった。1980年代に入ると中小規模の産業も生まれ、今日のグローバル化の厳しい競争環境の中で生き延びている。2006年2月からChinguetti海上油田の生産を開始し、他の油田も開発途上で、モーリタニアの経済・社会発展は強化されつつある。
■鉄鉱石
古来、製鉄に使われた鉱石は砂鉄(磁鉄鉱)であった。磁鉄鉱は比重が約5.2と商業的に利用できる鉄鉱石の中で最も大きく、流水による選鉱により純度の高い鉱石が容易に得られた。近代的な溶鉱炉による製鉄技術が確立されるまでは砂鉄を使ったたたら製鉄が主流だった。現在では露天掘りで大量に採取できる赤鉄鉱を使用した高炉による製鉄が主流である。
■金
gold,は原子番号79の元素。元素記号は Au。第11族元素に属する金属元素。貴金属の一種であり、単体の金属として古くから知られてきた。元素記号は Au であり、これはラテン語で金を意味する aurum に由来する。柔らかく、可鍛性があり、重く、光沢のある黄色(金色)をしており、展性と延性に富み、非常に薄くのばすことができる。
■ダイヤモンド
(diamond) は、炭素(C)の同素体の1つであり、実験で確かめられている中では天然で最も硬い物質である。日本語で金剛石(こんごうせき)ともいう。結晶構造は多くが8面体で、12面体や6面体もある。宝石や研磨材として利用されている。ダイヤモンドの結晶の原子に不対電子が存在しないため、電気を通さない。
■岩塩
rock salt, halite)は、鉱物として産する塩化ナトリウム(NaCl)のことである。岩石名でもある。海底が地殻変動のため隆起するなどして海水が陸上に閉じ込められ、あるいは砂漠の塩湖で、水分蒸発により塩分が濃縮し、結晶化したものである。歴史上では、イジリやテガーザなど西アフリカのサハラ砂漠中の塩鉱が知られ、サハラ交易によってガーナ王国、マリ帝国、ソンガイ帝国、オアシス都市などの経済的繁栄をもたらした。
■マダコ
Octopus vulgaris) は、タコ目・マダコ科に属するタコの一種。世界各地の熱帯・温帯海域に広く分布し、日本では一般にタコといえば本種を指すことが多い。浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息するが、外洋に面した海域に多く、内湾には少ない。昼は海底の岩穴や岩の割れ目にひそみ、夜に活動して甲殻類や二枚貝を食べる
■リシャット構造
Guelb er Richateとは、アフリカ北西部、モーリタニアの中央部に位置する巨大な環状構造である。リシャット構造体とも言う。直径は約50kmに及び、宇宙空間からでないと、その全容は掴めない。その形状から「アフリカの目」、「サハラの目」と呼ばれることもある。周囲はサハラ砂漠に囲まれ、標高100〜200mほどの高台の中に、窪地となったリシャット構造が存在する。構造内部は、同心円上に標高100mほどの山が幾重にも重なっている。発見当初は、隕石の衝突によるクレーターと思われていたが、調査の結果、特有の鉱物が存在しないこと、直径に比べて深さが浅いことなどから、これは否定されている。
■メド・オンド
Med Hondo、1936年 - は、モーリタニアの映画監督。フェスパコでグランプリを受賞した Sarraounia は、19世紀にフランス軍と戦った女王サラウニアの物語であり、アブドライエ・ママニの小説が原作。公式サイト
■アブデラマン・シサコ
Abderrahmane Sissako、1961年10月13日 - は、モーリタニアの映画監督。21歳からモスクワ映画学院で学び、初監督作 Le Jeu や第2作 Octobre はモスクワで制作している。Heremakono(英題Waiting for Happiness) は、フェスパコグランプリを受賞。Bamakoは第59回カンヌ国際映画祭の特別招待作品となり、第60回カンヌ国際映画祭では審査員をつとめた。
■ムハンマド・ウルド・アブデルアズィーズ
Muhammad Al-‘Aziz、Ould Abdelaziz、1956年12月20日 - は、モーリタニアの軍人・政治家。元大統領警護隊長。2008年にクーデターで実権を握り、2009年の大統領選で当選し、同年より大統領を務める。大統領としては第4代、国家元首としては第10代に該当する。2005年8月、マーウイヤ・ウルド・シディ・アハメド・タヤ大統領を打倒したクーデターで指導的役割を果たした。2008年8月、再びクーデターを主導し、シディ・モハメド・ウルド・シェイク・アブダライら政府首脳を拘束した。
■シディ・モハメド・ウルド・シェイク・アブダライ
(Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, 1938年8月18日 - )は、西アフリカのモーリタニアの政治家。2007年に大統領となったが、翌2008年にクーデターで政権が転覆された。同国大統領としては第3代、国家元首としては第7代に該当する。クウェートとの関係が深い。同国南部ブラクナ州の州都アレグ出身。アレグで初等教育を受けた後、トラルザ州の州都ロッソに移った。ロッソで中等教育を受けた後、セネガルのダカールで数学、物理学、化学を専攻した。後にフランスのグルノーブルに留学し、経済学においてDEA(博士課程研究免状)を取得した。 |
モーリタニア Mauritania
アフリカ北西部に位置する共和制国家。北西に西サハラ、北東にアルジェリア、東と南にマリ、南西にセネガルと国境を接し、西は大西洋に面する。大西洋沖の西にはカーボ・ヴェルデが存在する。首都はヌアクショット。アフリカ大陸の西側に位置するモーリタニアは、おおむね平坦で日本の約3倍の国土面積を持つ。全土がサハラ砂漠に位置するため、国土の90%以上が砂漠であり、中央部にリシャット構造と呼ばれる同心円状の特徴的な地形がある。

■ヌアクショット
フランス語Nouakchottは、西アフリカ、モーリタニア・イスラム共和国の首都であり、サハラ砂漠最大の都市である。大西洋岸に位置する。人口は1999年の推計で881,000人。大西洋に面し、港があるほかは砂海岸である。サハラ砂漠の端に位置し、砂丘の接近が深刻な問題である。
■ヌアクショット空港
Nouakchott International Airportは、モーリタニア・イスラム共和国の首都、ヌアクショットにある空港。
■シンゲッティ
Chinguetti は、モーリタニア北部の、クサールと呼ばれる古い交易拠点の一つである。アドラール台地にあり、アタールの北に位置する。13世紀にサハラ交易ルート上の拠点として建造されたこの小さな町は、エキゾチックな風景や歴史ある手稿の宝庫に驚嘆する人々を惹きつけ続けてきた。サハラの先住民たる旧市街に住む人々は、赤みがかった石と日干し煉瓦ででき、屋根にヤシの梁が渡されていた家で暮らしていた。

■ウアダン
Ouadane は、モーリタニア北西にある町。アドラール台地に位置し、シンゲッティの北東に当たる。1147年に創建され、ほどなくキャラバンの交易の拠点となった。1487年にはポルトガルの貿易拠点が置かれたが、16世紀以降町は没落した。
■アタール
Atar は、モーリタニアの都市。人口24021人(2000年)。モーリタニア北西部に位置し、アドラル州の州都である。アドラル高原の中心都市であり、博物館や空港、1674年に建てられた歴史的なモスクなどがある。アタールはサハラ砂漠のただなかにあり水の供給は重要事項であるが、近年モーリタニア政府の依頼を受けたロシア人科学者が地質情報と衛星から得られた地形情報をもとに大きな地下水脈を発見し、モーリタニア軍によってその発見は確認された。最終的には、アタールのすべての水をその水脈で賄えるようになると考えられている。
■ティジクジャ
(Tidjikja)は、モーリタニアの都市。人口18586人(2010年)。モーリタニアの中央部にあり、タガント州の州都である。タガント高原に位置し、サハラ砂漠の中にある街である。ティジクジャは1680年に建設された。この街はヤシの木と独特の建築様式で知られる。
■ズエラット
(Zouerat)は北部モーリタニア最大の都市で、ティリス・ゼムール州の州都である。人口は3万8千人(2005年)。ヌアディブーから延びているモーリタニア鉄道の東の終点であり、近郊のフデリック鉱山をから産出された鉄鉱石を、鉄道を使って運搬する。この貨物列車は一度に3輌のディーゼル機関車が200輌以上の鉄鉱石専用貨車を牽引するもので、文字どおり世界最長の列車である。
■ロッソ
(Rosso)はモーリタニア南部の都市。セネガルとの国境に位置する。トラルザ州の州都。アラビア語名はアル・クワリブ。モーリタニアで3番目に大きな都市である。フランスの統治下では、モーリタニアとセネガルは同じ仏領西アフリカに属していたが、独立後、セネガル川が両国の国境となったため、セネガル川北岸がロッソ・モーリタニア、南岸がロッソ・セネガルと、町は二国間に分断された。
■ウアラタ
Oualata, は、モーリタニア南東部の町。マンデ人やソナンケ人に近い農耕・牧畜民が最初に町を作ったと考えられている。彼らはモーリタニアのタガン高地 (Tagant) の断崖やティシット=ウアラタの切り立った岬に沿って暮らしていた。その地で、彼らはアフリカ大陸最古となる石造建築物を立てていたのである。

■フデリック
モーリタニア北部の都市。ティリス・ゼムール州に属する。サハラ砂漠の只中にあり、非常に乾燥した土地であるが、フデリックには鉄鉱石の大鉱山があり、ここから産出される鉄鉱石はモーリタニア経済の柱となっている。
■ヌアディブ
(Nouadhibou)は、モーリタニアの都市。人口は約9万人。人口は首都のヌアクショットに次いで第二の規模。西サハラの国境に近い。主な産業は漁業だが、内陸のズエラットまでモーリタニア鉄道が通じており、鉄鉱石などの積出港としての役割も果たしている。
■アタール
Atar)は、モーリタニアの都市。人口24021人(2000年)。モーリタニア北西部に位置し、アドラル州の州都である。アドラル高原の中心都市であり、博物館や空港、1674年に建てられた歴史的なモスクなどがある。近年モーリタニア政府の依頼を受けたロシア人科学者が地質情報と衛星から得られた地形情報をもとに大きな地下水脈を発見し、モーリタニア軍によってその発見は確認された。
■キファ
キファあるいはキファビーズ (Kiffa beads) はガラス粉を焼結した穴のあいたガラス玉(ビーズ)のこと。再生ガラスによるとんぼ玉の一種。1949年に民族学者のR. Maunyがモーリタニアのキファ市周辺で発見したことから『キファ』と呼ばれる。 縦縞模様のはいった二等辺三角形のものが有名。
■ボゲ
Boghe)はモーリタニア南西部、ブラクナ州の都市[1]。2000年現在の人口は37,531人。ボゲ県の県都である。モーリタニアとセネガルの国境であるセネガル川北岸に位置する。
■ブチリミト
トラルザ州の南部モーリタニアの都市である。市は、都市はしばしば景観の一部を巻き込むことができる大量の砂によって脅かされている。気候は非常に乾燥しており、温度は45°Cにも昇る。 人口は4万人ほどであるが、介入がしばしばある。
■カエディ
(Kaé臼粡)は、モーリタニアの都市。人口55,374人(2010年)。モーリタニア南部、セネガル川に面し、対岸のセネガルとの国境の町である。ゴルゴル州の州都である。首都ヌアクショットからは南東に435km離れている。カエディは市場町として、また地域の農業の中心として栄えており、またカエディ地方病院などがあるため地域の医療の中心となっている。
■ネマ
(Nema)は、モーリタニアの都市。国の南東部に位置しており、マリとの国境に近い。ホズ・エッ・シャルギ州の州都。都市部の人口は5〜6万人。郊外にはおよそ20万の人々が居住している。ネマはモーリタニアとマリの国境に近く、人々の往来が盛んである。
■ティシット
Tichit,は、モーリタニア東部のタガン高地 (Tagant) の麓にある町。建造されたのは1150年頃のことであり、独自の建築様式で知られる。現在のティシットの主産業はナツメヤシの栽培である。町には博物館もある。
■アドラル州
Adrar,はモーリタニアの州のひとつ。名前はアドラル高原に由来する。州都はアタール。

■ティリス・ゼムール州
モーリタニア最北の州。州都はズエラット。南をアドラル州、北及び北西を西サハラ、北東をアルジェリア(ティンドゥフ県、アドラール県)、東をマリ共和国(トンブクトゥ州)に囲まれる。州全域が砂漠であるが、州内のフデリックの鉄鉱石はモーリタニア経済の柱となっている。 ダイヤモンド・ウランが採れる。
■モーリタニア鉄道
Mauritania Railway、Chemin de fer de Mauritanieとは、モーリタニアのズエラットとヌアディブを結ぶ鉄道である。ズエラットには、鉄鉱石を産出するフデリック鉱山が存在しており、ここから沿岸部へ鉄鉱石を搬出するために建設されたのがモーリタニア鉄道である。路線はズエラットからシュームまで南下して、そこからほぼ西へ向かってヌアディブへ到着する。全長は717 kmあり、軌間は1,435 mm(標準軌)、最大軸重は26 t、全線非電化単線である。線路は概して西サハラとの国境を沿うように敷設されている。
外務省:モーリタニア・イスラム共和国
在モーリタニア日本国大使館
■宗教
イスラム教を国教とし、1991年の憲法改正でイスラム法(シャリーア)が正式に採用された。イスラム教徒の比率は99.1%である。
■教育
6歳から12歳までの初等教育が無償の義務教育期間となっており、その後6年間の総合中等教育を経て高等教育を行う。2003年の15歳以上の人口の識字率は51.2%である。
■モーリタニアの国旗
モーリタニアの国旗(モーリタニアのこっき)は、緑地に黄色の三日月と星があしらわれた旗で、1959年3月22日にモーリタニア憲法第 5 条で定められ、4月1日に制定された。翌60年11月の独立で正式にモーリタニア国旗となった。三日月と星はこの国の主要な宗教であるイスラム教のシンボルである。緑はイスラム教を象徴し、黄色はサハラ砂漠の砂を表している。国土の大半を占めるサハラ砂漠を緑化したいという強い希望を示している。
■国名
公式の英語表記は、Islamic Republic of Mauritania(イスラミク・リパブリク・オヴ・モーラテイニア)。通称、Mauritania(モーラテイニア)。国名はアフリカの地中海岸に位置したベルベル人の古代国家マウレータニア(現在のアルジェリアとモロッコ)からとられている。
1.面積:103万平方キロメートル(日本の約2.7倍)
2.人口:320万人(2008年 UNFPA)
3.首都:ヌアクショット
4.民族:モール人、アフリカ系
5.言語:アラビア語(公用語、国語)、プラール語、ソニンケ語、ウォロフ語(いずれも国語)なお、実務言語としてフランス語が広く使われている。
6.宗教:イスラム教(国教)
15世紀- アラブ系民族による支配
1902年 フランスによる支配の開始
1904年 フランス領
1945年 フランス連合植民地
1958年 自治宣言
1960年 フランスより独立(ダダ初代大統領)
1978年 クーデター、特別軍事政権成立
1984年 クーデター、タヤ参謀総長政権掌握
1992年 タヤ大統領選出
1997年 タヤ大統領再選
2003年6月 クーデター未遂事件
2003年11月 タヤ大統領三選
2005年8月 タヤ大統領不在時に軍事クーデター

軍部暫定政権発足
2007年3月 アブダライ大統領選出
2008年8月 クーデター、軍事政権発足、アブデル・アジズ将軍が政権掌握
2009年7月 大統領選挙、アブデル・アジズ大統領選出
■主要産業:農牧業(ソルガム、粟、米、牛、羊)
■主要貿易品目(2009年)(1)輸出 鉄鉱石、原油、魚介類(2)輸入 石油開発機器、石油製品
■ウギア
Ouguiya)は、モーリタニアの通貨単位。ISOコードはMRO。補助通貨はコウムで、1ウギア=5コウムである。モーリタニアは1960年にフランスから独立したが、西アフリカ地域では関税同盟と共通通貨CFAフランを軸とする経済協力関係が敷かれることになった。
■ポリサリオ戦線
Polisario、西サハラにおける独立国家建設を目指す武装組織。同地域を実効支配するモロッコと対立。アルジェリアの支援を受ける。公式名称はサギア・エル・ハムラおよびリオ・デ・オロ解放人民戦線 。構成メンバーは約1万人と見積もられる。
■政治
1984年にクーデターで政権を掌握したタヤ大統領は、1990年代初頭、1992年及び1997年の大統領選挙で勝利を収めた。しかしその後、クーデター未遂等が発生し、2005年8月にはタヤ大統領不在時に軍部が無血のクーデターにより政権を掌握した。その結果「正義と民主主義のための軍事評議会」が設置され、現在民主化プロセスを進展中。
■アラブ・マグレブ連合
Arab Maghreb Union: AMUとは、北アフリカの通称、マグレブと呼ばれる5ヶ国が同じ歴史、文化を共有した背景から連帯、進歩、諸権利の保護を目的とし、1989年に創設された経済協力機構。本部はモロッコのラバト。
■アフリカ連合
アフリカの国家統合体。アフリカ統一機構 (OAU) が、2002年に発展改組して発足した。エチオピアのアディスアベバに本部を置いている。アフリカ統一機構からアフリカ連合への移行のため、2000年7月のロメOAU首脳会議でアフリカ連合制定法(アフリカ連合を創設するための条約)が採択され、各国の批准を待って、2001年に発効した。
■アラブ連盟
League of Arab States、直訳は「アラブ諸国連盟」は、アラブ諸国の政治的な地域協力機構。第二次世界大戦末期の1945年3月22日創設。本部はカイロにある。加盟は22(21カ国と1機構)。 現在の連盟事務局長はエジプト前外相のナビール・エル=アラビー。参加各国の代表からなる理事会が最高決定機関で、その下に実行機関である事務総局や常任委員会、共同防衛理事会、社会経済理事会、ほか専門の諸機関がある。
■後発開発途上国
Least developed country)とは、国際連合(国連)が定めた世界の国の社会的・経済的な分類の一つで、開発途上国の中でも特に開発が遅れている国々のことである。略語としてLDCと表記される。最貧国という呼称も定着しているが、これに区分される国は2012年4月現在で48か国(つまり世界の国家のうち、4分の1ほど)もあるため、実情を示す上では不正確といえる。また第四世界と呼ばれることもある。

■ウッドサイド・ペトロリアム
(Woodside Petroleum, ウッドサイド石油) は、石油調査・製造の会社。本部は西オーストラリア州の州都パースに置く株式公開会社。メキシコ湾の数地域 モーリタニア沖のシンゲッチ油田(アルジェリアと共同)に、石油・天然ガス採掘所があり、ケニヤ、リビア、シエラレオネ、カナリア諸島域に所有権がある。
■モーリタニアの経済
国民の3割が貧困線以下の生活をしている貧しい国であり、2005年と2008年にクーデターが発生するなど、不安定な政情が経済成長の足枷になっている。モーリタニアの労働人口のおよそ半数は農業と畜産業に従事しているが、砂漠気候による旱魃や害虫の被害により、生産性は低い。
■外交
外交面では非同盟を軸として穏健中立を貫くとともに、フランスを始めとする先進諸国との関係強化を進めている。アラブ・マグレブ連合(AMU)のメンバーとしてイスラム諸国との域内協力に積極姿勢を示す一方で、1999年10月にはイスラエルとの外交関係を樹立した。しかし2008年に始まったイスラエルによるガザ侵攻に反発し、2009年にイスラエルとの外交関係を断絶し、再び反イスラエルに転じている。
■社会問題
ベルベル人とアラブ人の混血である、イスラム教徒のムーア人(モール人)が社会の上層を占める。ムーア人と黒人が対立する構図は、独立後も続いている。独立後も奴隷制が続いていたが、1980年に公式には奴隷制が廃止された(公式には世界奴隷制消滅宣言)。ただし、その後も実態として虐待を伴う奴隷制は続き、若干の賃金が与えられているだけとの指摘もある。2003年には再び人身売買を禁止する法律が公布された。
■ガバージュ
少女を強制的に肥満化する風習があった。砂糖を加えたラクダの乳や雑穀のかゆ、クスクスなどを大量に飲み食いを強制され、飲み食いを拒否すれば万力でつま先をつぶされるなどの罰を受けるということが伝統的に行われてきた(ガバージュと呼ばれる)。モーリタニア政府が2001年から行ってきた調査によると、少女時代に「ガバージュ」(強制肥満化)を受けた女性は5人に1人である。政府は独立以来ガバージュを撲滅するキャンペーンを続けてきた。
■マーウイヤ・ウルド・シディ・アハメド・タヤ
(Maaouiya Ould Sidi Ahmed Taya, 1941年 - )はモーリタニアの政治家・軍人。大統領としては第2代、国家元首としては第5代。フランスで軍事教育を受けたのち、軍事・政治的役職を歴任。1984年12月にクーデターでハイダラ政権を打倒し、国家元首に就任。1992年に大統領職に就いた。2005年にクーデターで大統領職を追われた。

■モクタル・ウルド・ダッダ
(Moktar Ould Daddah, 1924年12月25日 - 2003年10月14日)は、モーリタニアの政治家。1960年、モーリタニアのフランスからの独立後、まず内閣首長となり、1961年初代大統領になった。1978年まで、三期にわたり大統領に選任された。モーリタニアの富裕な家庭に生まれた。パリに留学し、法学を学んだ。ダッダはモーリタニア出身者で最初に学士号を得た人物である。シャルル・ド・ゴールの娘と知り合い、結婚した。この結婚は、フランス植民地であったモーリタニアでの彼の昇進を有利にするものとなった。

|
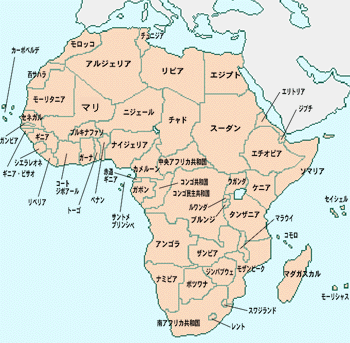
![]()

