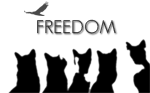ピープルズニュース 3月10〜11日にわたって、郡山で開催された「原発いらない地球(いのち)のつどい」。参加企画として、3月10日に行われた「原発労働者の労働運動─経験と課題」を取材した。原発下請労組「全日本運輸一般・原子力発電所分会」分会長・斎藤征二さんの講演と、講演後のインタビューを基に報告する。斉藤さんは、「どこにでも話をしに行く」とのことで、頭が下がる思いだ。 福島での事故収束作業では、「緊急事態」を口実に多くの労働者が、被曝労働を強いられている。住民も放射能に苦しめられている。放射能汚染に苦しむすべての人々と、被曝労働者の連帯を目指すために、かつての原発分会、分会長である斉藤さんの話しを聞き、新たな取り組みを構想したい、と主催者は語る。 まず、この日の斎藤征二さんの話を要約する。斎藤さんは玄海原発で、米企業であるウェスティングハウス(当時の国内原発はすべてアメリカ製)の社員が主導する言葉の通じない中での配管作業を経験した。以下は、斉藤さんの発言要旨だ。 (以下一部全文と写真説明は1442号を入手ください。購読申込・問合せはこちらまで) http://www.jimmin.com/mail/postmail.html ピンハネ・使い捨て―前近代的労働慣行が横行する原発 私自身の作業箇所によってだ。その直後、国、県等関係機関が立ち入り調査に入り、次々に違法工事が発覚し、5月から始まる定期検査が中止になり、その点検に呼ばれていた多くの作業員が一斉にクビとなったため、私は、原発下請け労働者の労働組合を作る決意をした。職場の中で組合運動を展開させることは、不可能。バレればクビになる。暴力団による妨害もあった。仲間とともに作業員の各家庭をまわり、作業員の家族を交えて説得し、1981年に、183名の組合員を集め、組織化することに成功した。 原発に於ける最末端の多くの下請け労働者には、労働契約が交わされていない。当時元請けに支払われた、 3・7〜4万円の賃金が一次、二次、三次という多重構造によりピンハネ(中間搾取)され、末端では1日7000円足らずでの労働者も多くいる。その最末端である彼らの作業には技術はまったく不要で、役割は一言で言えば「被曝すること」だ。 ウエスによる拭き取り作業などの単純作業だが、彼らこそが最大の被曝労働者であり、まさに放射能への特攻隊だ。原発内には無数の配管が張り巡らされており、無数のバルブが作業の困難な高所に集中し、そこから蒸気が漏れる。タンクに亀裂が生じたり、ポンプの故障も多発している。それらから撒き散らされる汚染水が、高温・多湿のため床にこびり付き、それを剥がし取る作業―それが、原発内作業の基本だ。「大きな地震に見舞われればどうなるか?」心配だったが、それが今、福島で、起きている。 血を吐き倒れる原発ジプシー 私自身、半年間の現場作業によって受けた被曝量は22・6ミリSVに過ぎないが、その後、緑内障で両眼を手術し、甲状腺に2ミリほどの血の塊ができ、摘出。そして心筋梗塞。脊髄、骨髄にも異常が起きるなど、身体を全部壊した。被曝と健康被害の因果関係は認められていない。だが、低レベル内部被曝(チリ、ホコリ等吸いこむ)による健康被害だと、私は確信している。多くの労働者が、原発ジプシーとして全国の原発を転々とし、職場で血を吐き、倒れている。労働契約も交わされない作業員が倒れても、会社は関知しない。自己責任だ。彼らの多くは、「被曝者管理手帳」の存在さえ知らない労働者も多い。教えられてもいないからだ。病気になった時、初めて自分には何の保証もないことに気づく。突然死も多い。命を預けるマスクのフィルターには欠陥品が多く、線量を感知するアラームメーターにも故障が多い。つまり、運が悪ければとてつもない被曝を受ける。《低レベルでも被曝する》ということを立証し、認めさせることが重要だ。 被曝を押しつけられる下層労働者 この国最大の危機を回避するために働く下請け労働者の多くが、命を削りつつ、組合はおろか労働契約も交わされないまま、被曝労働を強いられている。その収束・廃炉のために、今後100万人単位の労働者が必要とさえ言われる。事故収束後も、廃炉でさらに高線量の被曝作業が待ち受け、膨大な作業員を必要とする。廃炉作業に伴うリスクは、いったい誰が背負うのか? 斎藤さん達の労組結成から2年後、1983年1月、石川県羽咋郡志賀町で行われた、地元の広域商工会主催による原発講演会で、当時の高木孝一敦賀市長は、莫大な交付金によるメリットを挙げた後、こう言い放った―「その代わりに、100年経って障がい児が生まれてくるか、わかりませんよ。けど、今の段階では、(敦賀原発を)おやりになった方がよいのではなかろうか。こういうふうに思っております」 ―敦賀原発は82年に着工され、87年に営業運転を開始した。悪名高い、原発専門の最大手人材派遣会社=アトックスは、首都圏から何も知らない20代の若者を集め、福島にも送り込んでいる。彼らの主な作業は、ウエスによる見えない汚染物質の拭き取りだ。それが原発内作業の基本であり、被曝労働の実態だ。 行き場のない人、訳ありの人、差別される人々が、被曝労働に従事し、原発内でも差別を受け続けている。だが、彼らなしに原発を支えることはできない。そうした環境に労働運動を持ち込むことが極めて困難なことは、容易に想像がつく。反原発運動内でも、分断と対立がある。 仙台に住む僕達が「反原発」を叫ぶほどに、福島の人々は硬直してしまい、分断が深まっていく現実がある。だからこそ、反原発運動にはこれまでの労働運動とは違う運動が必要だ。被災地とも原発労働者とも繋がりを持つことの重要性だ。地域再生のためにも、地域や課題を越えて連携することが必要だ。
〈ニッポン人脈記〉石をうがつ:42012年9月5日 「原発で働けば世界で通用する」と親方に言われ、福井県の美浜を皮切りに、67年から全国の原発を渡り歩いた。事故隠しの敦賀原発はその後、放射能漏れも起こして6カ月の運転停止に。斉藤ら多くの作業員は仕事がなくなり、クビになった。 樋口健二(ひぐち・けんじ)(75)。被曝(ひばく)労働の問題をずっと掘り起こしてきた写真家だ。樋口は長野県の農家に生まれた。高校卒業後、川崎市の製鉄所で働いたが、デパートの企画展でロバート・キャパの戦場写真を見て人生が変わった。倒れる兵士、占領から解放された民衆。会社を辞めて写真学校に通った。66年7月、「公害病の患者が自殺」という見出しの小さな記事が新聞に出た。 四日市ぜんそくに苦しむ男性が「仏さまになって楽になりたい」と首をつったという。患者の苦しみを伝えたい。そう思い立った樋口はすぐに三重県の四日市市に入ったが、最初はどの患者からも取材を拒まれた。「写真で金もうけをするつもりか」と罵倒されたこともある。妻子を持つ身、郵便局のアルバイトで食いつなぎながら四日市に通った。6年を経て出した写真集は、国連のコンテストで入賞を果たした。 ルポライターの鎌田慧(かまた・さとし)(74)。樋口が行く先々に、鎌田の名前が残っていた。鎌田は青森の高校を卒業して上京し、働いていた印刷工場を会社の都合で一方的に解雇された。その体験が、労働者や住民の側の視点で書き続ける原点になっている。「原発は危険だ。でもそれだけじゃない。金の力で地元に言うことをきかせようというのが嫌だった」 鎌田はいま、「さようなら原発」集会と1千万人署名活動の呼びかけ人として、大江健三郎(おおえ・けんざぶろう)(77)、澤地久枝(さわち・ひさえ)(82)、内橋克人(うちはし・かつと)(80)、落合恵子(おちあい・けいこ)(67)、坂本龍一(さかもと・りゅういち)(60)らと、うねりの先頭に立つ。福島の原発事故の後、樋口の仕事は改めて注目され、50を超す内外のメディアから取材を受けた。 集会に呼ばれては各地を巡り、下請け労働者の被曝なしでは成り立たない原発の現状を説く。「俺は売れない写真家。売れてる奴を見ると、俺は不幸な道を選んだと思う。でも、俺の被写体は俺よりもっと不幸を背負っている」樋口が取材した原発労働者は150人にのぼる。病に倒れ、支援のないまま亡くなった人も少なくない。ボロ雑巾のように捨てられた人たちへの鎮魂の思いを胸に、伝え続ける。(大久保真紀) |