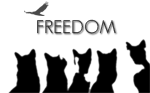〈人生の贈りもの〉石毛直道(74)(2012/11/30朝日新聞)
民族学者
■もとは考古学 探検部きっかけ
――民族学を研究して半世紀。いつからこの道を志したのですか
もとは考古学少年だったんです。国民学校の教師だった父とともに千葉県内を転々とし、気づいたら縄文時代の遺跡の発掘に参加していました。中学時代には貝塚遺跡の論文めいたものも書き、大学は考古学研究室があった京大を志望。数学ができなくて、2浪してなんとか入りました。
――それがなぜ、違う道に?
外国への憧れもあって、海外に行けそうな探検部に入ったんです。2回生の時、大阪市立大教授だった地理学者の藪内芳彦さん(故人)を隊長とする南太平洋のトンガの調査に参加しました。専攻は考古学なんで、現地で貝塚を発掘しようと思った。ところがトンガ人は毎日のように貝を食べ、食べかすを裏庭に捨てるので島中、貝塚だらけです。住民の食文化が浮き上がってくるのが面白かった。それこそが、民族学だったんです。
――民族学への転換は、それが契機だったのですか
そうでもない。卒論はポリネシアの石器を調べて太平洋考古学で書く予定でした。ところが主任教授から「縁がない分野で評価できない」と言われ、急きょ方針を変更。稲穂摘み用の石包丁を調べました。イネは沖縄など島伝いに伝来したという柳田国男説を疑い、「中国・長江下流域から海を渡り日本列島と朝鮮半島南部へ来た」という新説をまとめたら専門誌に載った。
かなり注目されました。考古学と民族学の間の壁は当時から低く、互いに出入りしていました。その頃、考古学講座の助教授だった樋口隆康さん(93)に民族学の研究会に連れて行ってもらったものです。所属は大学院でも考古学のままでした。
――探検部の活動に触発されたそうですね京大の院生だったとき、探検部は多くの謎が残されていたニューギニア中央高地調査を計画しました。インドネシアとの合同探検隊が成立し、私は探検部の先輩で朝日新聞記者だった本多勝一さん(81)らと現地の住民の暮らしを研究する「人類班」を結成。延べ10カ月間、現地の住民が、つい10年ほど前まで日常的に使った石器を調べました。
それは考古学と民族学の接点にあたる調査でした。帰国して間もなく大学院を中退して、京大人文科学研究所に入りました。新規採用の公募に応じたのが私1人だけで、後に国立民族学博物館を創設した梅棹忠夫さん(故人)の助手にしてもらいました。
■食の研究、原点は昔のひもじさ
――民族学で「食」をテーマにしたのは、食糧難だった子ども時代とかかわりがあるそうですね戦中戦後に育った私たちは「サツマイモ世代」です。私の家族は空襲で2度も焼け出され家財を失い、裕福でなかったうえに教師だった父の立場もあって闇市とは無縁だった。白米など望むべくもなく、当時、一生分のサツマイモを食べた感じです。それが私の原点です。食いしん坊で、ひもじくて、食べ物に憧れ、やがてこだわりを持つようになったのです。
――京大人文研の助手だった1969年、最初の著書「食生活を探検する」を出してから、研究は本格化します
あの時分、安月給なのに大食い、大酒飲みでね。若手の学者にも割引する京都独特の「学割」の慣例があったものの、飲食店に相当ツケがたまっていたんです。それを結婚前に清算するため、本で当てて稼ごうと考えました。幸い、太平洋やアフリカでの民族学調査の際、関心が強い食べ物について克明に記録、資料収集していたのが役立ちました。
よく売れて、借金を返すことができました。しかし学者の卵として一般向けの著作だけではまずいだろうと、すぐに世界の台所様式を調べた堅い論文「台所文化の比較研究」をまとめました。探検部の経験を生かして、コロンブスが新大陸を発見して世界が急速にグローバル化する以前の、15世紀の世界の食文化についても論文を書いてます。
――「食」からの民族学的なアプローチは独創的でした
当時の専門家はコメなど個別の課題には取り組んでいましたが、食を総合的にとらえる研究はありませんでした。栽培植物が専門の大阪府立大教授の中尾佐助さん(故人)、中国食物史をまとめた大阪教育大教授の篠田統(おさむ)さん(同)ら、ごく少数の先駆者に教えられながら、未開の分野を展開していきました。
――しかしご自身初の学術賞は「食」ではなく、「住」に関する論文でした
世界各地を対象にした「住居空間の人類学」(71年)で若手を対象とする唯一の民族学賞・渋沢賞(民族学振興会)をいただきました。「食」以外の研究もけっこうあるんです。
世界各地での現地調査にもとづく環境と文化の考察とか、島原半島の巫女(みこ)さんといった民間信仰論や日本文化論とか、いろいろ挑戦しました。でも、あれこれやっても、最後には「食」に関心が向く。81年、イギリスのオックスフォード大で開かれた国際的にも初めての「食文化」の研究集会に、アジアからただ1人参加しました。列席した欧米の研究者は、みなその国の食文化研究の創設者でした。「未開の分野を率いる世界の研究者の一人なんだ」と実感できて、うれしかったですね。

BACK
■動物園できるほど多種類を胃袋に
――2003年に随筆「食べるお仕事」を刊行されました。タイトルを読むだけで楽しそうですね
もう手遅れですが、食の研究を選んで、今になって「しまった」というのが、一番実感に近いんです。私の研究対象は宮廷料理とか美食、グルメではなく、民衆食です。研究のために食べ過ぎて糖尿病になっても労災認定はしてくれそうにない。食中毒も10回どころではありません。パリで食べた生ガキにあたって、ウィーンに移動中の列車ではトイレから出られませんでした。イタリアでは1日4〜5種類ものパスタや肉のコースをこなす。これは苦痛です。始めたころは「これで食いっぱぐれない」と考えていましたが、浅はかでした。好きなことを仕事にしてはいけません。食文化研究は健康の敵です。
――でも「鉄の胃袋」のニックネームがついてますね
研究では多くの食べ物にあたる必要がある。みんな食べているのだから、だいたい平気です。大切な食べ物を出されて「嫌」とも言えない。食べざるを得なければ、いかにもうまそうな顔をする。厚意に応えたいのです。東南アジアの山間部で、寄生虫やウイルスの心配がある貴重品のブタの生血を勧められたことがあります。覚悟して黙っていただきました。
ヘビ、ワニ、シマウマ、ラクダ、オオサンショウウオ……。動物園ができるほど多くの動物が私の胃袋を通り過ぎました。麺類初の研究書「文化麺類学ことはじめ」(91年)では、世界中の麺類を数百食は食べました。研究では、対象となったあらゆるものを食べることが欠かせません。その結果、中国で始まった麺類の食文化は西方に伝えられ、ペルシャからアラブ世界に広がり、シチリア島からイタリアに至ったという結論に達しました。
――それまで食の研究はほとんど手をつけられていませんでした。学界から奇異な目で見られませんでしたか
当時の研究の主流は民族の歴史や社会組織、宗教。食は「趣味の世界」「遊び」のように受け取られ、あえて触れない人もいました。だから私も初めは遠慮するところがありました。一方で「他人がやっていない、面白いことを始めたね」と認めてくれる人もいて、励まされました。
探検は他の人が行っていない未知の所を目指します。それは独創性を最も尊重する学問の神髄に通じます。食文化を開拓するにあたって、私は人間と動物との違いを料理や食習慣から特徴づける「人間は料理する動物である」「人間は共に食べる動物である」という文化論を提唱しました。「苦しいけれど世のため、人のため。この道一筋」という学者もいますが、私は楽しみたい。自由であることが、学者のいいところなのです。
■「大食軒酩酊」、退職後も喜び尽きず
――国立民族学博物館長を退かれて10年。悠々自適ですか
館長時代の6年間は、自分の時間がなかった。それでも週末を研究にあてて頑張って、年に1冊は本を出し、海外での研究発表、学術雑誌への寄稿を続けました。退職後は自宅近くにつくった研究室で若い頃のように研究に没頭するつもりでしたが、相も変わらず「日曜学者」のまま。生産力は上がってませんね。時間に余裕ができた分、遊んでます。
2日に1度は「スーパー銭湯」へ。電動自転車で片道10キロ以上かけて行くこともあります。しかし70歳を超えて、40年乗ってきたオートバイは終わりにしました。好きだったパチンコも、1年ほど前から中断しています。職業病といえる糖尿病以外、悪い所はない。健康法は意識してません。
――酒とたばこは?
一番気にいっている私の雅号は、飲み仲間だった作家の小松左京さん(故人)が命名してくれた「大食軒酩酊(めいてい)」です。大食に加え、生まれつきの酒好きです。七五三詣での5歳の時、樽酒(たるざけ)をひしゃく1杯飲んだそうです。「チュウの石毛」とも呼ばれてました。一番安い焼酎を愛好していましたから。小松さんとは京大の助手当時からのつきあいでした。
2人とも大阪北部に住んでいたこともあって、「今晩どう?」と誘いあう間柄でした。彼と一緒に飲む機会が、一番多かったな。6年前から「日本酒で乾杯推進会議百人委員会」の代表を務めてます。日本酒で日本文化を思い起こそうという趣旨のもと約3万人の会員がいます。各地で懇親会やシンポジウムを開き、酒造メーカー自慢の日本酒を楽しんでます。たばこは世間がうるさくなっても、やめるのは「軟弱だ」と小松さんと誓い合い、世間に迷惑をかけないように吸ってきました。酒もたばこも自己責任です。
――料理もプロ並みとか
貧乏学生でしたから、京大時代は一緒に考古学から民族学に転進した松山市の坂の上の雲ミュージアム館長、松原正毅さん(70)と腹いっぱい食べるために自炊したもんです。今もレシピ本20冊を愛用し、包丁を握ってます。プロが90点なら、家計や健康を考えた主婦の家庭料理と同じで60点を目指してやってます。
――師匠の梅棹忠夫さん(故人)を皿洗いで酷使したそうですね
リビア砂漠の探検の際、干しダラを水で戻し、鶏のささ身を調理したのを、梅棹さんは「刺し身が出た」「天才的な包丁人」と本に書いてくれました。弟子の私が料理長なもんだから、梅棹さんには遠い泉で水をくみ、皿洗いをしてもらいました。今では恐れ多くも伝統料理研究家の奥村彪生(あやお)さん(75)、中国料理の程(てい)一彦さん(74)に、私の料理を強要するに至ってしまった。この20年ほど、大晦日(おおみそか)に自宅で天下の料理人である2人を、私の手料理でもてなすしきたりになっています。
■異文化に触れ、国境超えた発想を
――日本人はまだ、世界の民族問題に疎いとされています
島国の日本は海外との接触が少なく、本格的な民族問題の経験も乏しかった。しかし今は世界規模の冷戦もなく、かつてのような外貨持ち出し制限や立ち入り禁止地帯も減った。世界はグローバル化したのです。国家や民族など関係なく、民衆同士が直接、触れあっている。環境は整っているのだから、若いうちに海外に出て、どしどし異文化を体験してほしい。
民族学についても、新しい世代を中心に新しい民族学を築く可能性は大きく広がっています。期待される役割も大きい。民族学では自分で調べた第一次資料なしでは研究できない。博物館のリフレッシュもできない。情報収集が容易なコンピューターの出現で調査の手法も変わってきたといわれますが、優れた研究を打ち立てるためには、現地第一主義は変わらないでしょう。
――グローバル時代に求められる民族学とは
戦前の民族学は、国の植民地の統治政策と結びついた側面もありました。しかしこれからは国家の単位で物事を考えず、人類という発想に立ってほしい。「人口が増えると国力が盛んになる」という拡大主義の国家理念では人類は先細りする。資源をどんどん消費していったのが近代文明ですから。将来を考えると、残念ながら人類滅亡のシナリオが描けるようになってきた。
希望のもてるものを見いだすことはまだ難しいのが現実です。資源をあまり使わず、人々が生きがいを感じ、楽しくなるためにはどうしたらいいのか。心の中に植えつけられる豊かな文化やスポーツ、芸能などを考えるべきでしょう。民族学もその一翼を担っています。人類の将来を切りひらくためにも、国家を越えた民族学の探究が大切です。
――民族学の過渡期に、世界を渉猟して半世紀。振り返っていかがですか
結果的に少年時代からの「知らない所へ」の念願がかない、これまで90カ国ぐらい訪れました。なるべく行ったことのない、未知のところにどんどん出向きました。退職後も妻と年に1回は、仕事抜きで海外に出かけています。結構、楽しんでますよ。去年はブルガリア、今年はスリランカに行きました。
普通、考古学の発掘調査や民族学のフィールド調査は一つの地域に何年もかけて長期滞在する。でも、そういうのは私の性に合わない。それで比較研究のため、世界各地をできるだけ多く巡るという、うまい口実を見つけたといえます。食べ物の研究は、海外を広く知る願いにぴったりでしたね。食べることは人間の基本です。国境を越えて歴史、社会、文学などあらゆるものにつながっている。「食」の研究はまだまだ大きな可能性を秘めている分野だと思います。
(聞き手・天野幸弘)
◇
いしげ・なおみち 1937年11月、千葉市生まれ。京大人文科学研究所助手から甲南大助教授などを経て97〜03年、国立民族学博物館館長。著書に「食生活を探検する」など。現在「石毛直道自選著作集」を刊行中。大阪府茨木市在住。
http://digital.asahi.com/
articles/OSK201211290066.html

BACK |