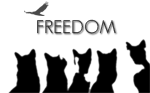〈人生の贈りもの〉柳田邦男(76)(2012/10/26朝日新聞)
ノンフィクション作家
■「失礼です」少女は言った
――報道、とりわけ悲惨な事件事故や災害の報道には「原罪」がつきまとう、と後に雑誌に書いておられます。
事実を詳しく報じることが被害者の心の傷になるという二律背反のなかで、報道する。安全の確立に寄与するなら、遠回りでも償いになりうるのではないか、と。航空機事故の取材をなぜ始めたのですか東京オリンピックの前の夏に東京社会部に異動して、五輪のバレーボールなどを担当。
2年後の1966年春、全日空機が羽田沖に墜落、カナダの旅客機が羽田空港着陸時に炎上、イギリスの旅客機が富士山上空で空中分解と、連続して航空機事故が起きて、300人以上が亡くなったのです。なぜこんなことが起きたのか、先輩たちと取材班をつくりましたが、みな忙しくて、いつのまにか僕だけが残った。「とことん取材して、これだという決定打だけ報道しろ。安易な推測記事はいらない」とキャップが言ったのです。それで専門家のもとに通ってじっと勉強するうち、信頼して話してもらえるようになりました。
――「原罪」の体験は
羽田沖事故で両親を亡くした少女が、新盆の前、ピアノの練習に励む姿を撮らせてもらったとき、鍵盤を動く指にカメラが向けられた途端、彼女の指がぴたっと止まりました。「失礼です」と言って。僕は凍りつき、おわびしました。少女の繊細な心に、思い至らなかった。正義感で取材しても、相手はさらしもののように感じたり、傷ついたりすることがある。それを認識して、配慮して取材すれば、印象が違うのではないか……。
――今度は実名で「文芸春秋」に羽田沖事故のことを書きました
手に持つロザリオを首にかけて亡くなった乗客がいました。なぜなのか。それを知ったとき、書ける、書かなければと思いました。
――5年取材して「マッハの恐怖」という本にまとめました
文春のデスクが、フジ出版という小さな出版社を紹介してくれて。特ダネ風に書いた文章など、80カ所も注意されました。20年たっても腐らないものを書け、と。――それで大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。2年後に、38歳でNHKを辞めました72年の4月が授賞式で、そのころは辞める気はなかった。活字として残る本への愛着が募った、ということはありますが。
決定的に辞めようと思ったのは74年。いよいよ管理職を命じられそうで、これで終わりだと思ったの。生涯記者でいたかった。それで、明日内示が出るという7月の夕方、辞表を出しました。当時の妻が、72年秋に保育園児の次男が交通事故にあって以来、心を病んで大変だった。そういう家庭の事情もありました。職場の誰にも話しませんでしたが。
■「意味ある偶然」つなぐ出会い
――ご自身の本のなかで「空白の天気図」が、一番好きだとか。
原爆のひと月後に枕崎台風が上陸して、広島県でとりわけ多くの犠牲者が出た。なぜだったのか。懸命に観測を続けていた広島地方気象台の人々を書きましたNHKに1974年夏に辞表を出して、すぐ家族を連れて広島に取材に行きました。広島放送局時代から少しずつつかんだ話で、被災者から見れば折り重なる「複合災害」なのですが、専門家は原爆と気象と分かれていて、二つを結びつける視点がまだなかった。
38歳でNHKを辞めて、食えるか食えないかわからない。雑誌に書いたりテレビに出たりしても、蓄えもない。それでもやっぱり、しっかり取材しようと思って、生活をかけて書いた本でした。気象台の人に片っ端から会い、記録を見せてもらうと、原爆の後に黒い雨が降った記録がほんの数行あって……。取材中、ものすごく気持ちが高揚していました。
――続けて、がんの取材に入ります
週刊現代でがん治療を連載したのが始まりでした。当時の国立がんセンター研究所長に「死とは何ですか」と尋ねると、「死とは、その人の人生が短期間にインテグレート(集積)されて出てくるものではないか」と。まさにそのように生きた患者さんたちの話を、「ガン50人の勇気」と題して「文芸春秋」79年11月号に書きました。それを、精神科医で前立腺がんの闘病中だった西川喜作さんの机の上に、同僚の誰かがそっと置いた。西川先生が読んで、手紙をくださって。その出会いが決定的でした。
――西川さんは、国立千葉病院(現・千葉医療センター)の精神科医として自分の病状と心理を観察し、死を前にした人がよりよく生き抜くのを支える「死の医療」が必要だと考えて、自分の体験を書きました。死後に出版された西川さんの「輝け 我が命の日々よ」は、胸に迫ります
伴奏者のように僕が話を聴いたのは、最後の半年。西川先生は、揺れ動く心をありのままに見つめて、日記に書き、率直に話してくださった。病を得たとき、人は健康なときには見えないものに気づき、感性がみずみずしくなる。雑草にさえいとしさを感じて、踏んではいけない、というような。「意味のある偶然」という言葉が僕は好きですが、81年10月、危篤の連絡をもらって病院にかけつけた日に先生の本のゲラが出た。
枕元に置いて手で触れてもらい、僕が耳元で「先生の記録が本になるのです」と話しかけると、何か大声を出された。廊下にいた新潮社の編集者が「お世話になりました、とおっしゃいました」と。聴覚は最期まで生きているといわれますが、先生に伝わった。
死に行く人の心理をきちんと見つめたいとおっしゃっていた西川先生は、自分のなしとげたことを確認し、納得して旅立った。亡くなったのは、4時間後でした。先生から託されたたくさんの記録をもとに「『死の医学』への序章」という本を書いたのは、5年後。僕が50歳になってからです。
■僕の心には弓矢が刺さったまま
――生と死の取材を続けながら、ご自身の生活も大変でした
次男は、中学時代に目にひどいけがをして恐怖に襲われたことをきっかけに、様子がおかしくなりました。長男は脳炎の後遺症で発作を起こすことがあり、後に別れた妻は心の病。20年くらい、毎日が修羅場みたいでした。「なんとかなるべさ」「しかたなかんべさ」という、お袋のあの口癖が、僕のなかに息づいていたのでしょうね。
――次男の洋二郎さんが25歳の夏、自死を図り、11日後に亡くなりました。手記を、翌1994年の「文芸春秋」4月号と5月号に刻みつけるように書きました
彼がこの世に生きた証しを、僕は絶対書かなきゃいけないという思いが募って。洋二郎が亡くなったのは93年の8月。まず、ごく親しい人に9月に手紙で知らせました。そして「文芸春秋」の編集長が新年に来て、帰ろうと腰を上げたとき、とっさに話した。吐き出すように書きました。
――加筆して、95年に単行本「犠牲(サクリファイス) わが息子・脳死の11日」を出します
雑誌を読み返したら粗かった。もっと、彼の25年間を、彼が独白のようにノートにつづってきた文章を、きちんと位置づけなければと思いました。彼がこの世に生きたということが、誰にも壊されることなく厳然としてあった。人間存在の「破壊し得ないこと(indestructibility)」というキーワードで書きましたが、洋二郎の好きだった言葉です。
――読者から数百通の手紙が寄せられて、単行本「『犠牲』への手紙」に結実しました
切実な手紙が多かった。「犠牲」は、死にたいと思っている人に悪い影響を与えるのではないかと危惧しましたが、僕としてはやむにやまれなかった。単にいのちを断ったという話ではなく、彼の生き方、いのちの形を書きたかった。「死ぬのをやめて生きようと思いました」という読者の手紙に、救われた思いがしました。
――洋二郎さんの言葉で、親には突き刺さる言葉がありました。「親父(おやじ)は作家だろ、作家なら、自分のこと書けよ、この家のなかの地獄を」
洋二郎に、許せとは言わないけれど、一生書いていくなかで応えていくしかないと思っています。彼の死によって僕の心に突き刺さった弓矢は、いまだに抜けないし、抜いたら私は死んでしまう。
ものすごく痛いけれど、その痛みに耐えながら、いつまでも抜かないでおかなきゃいけない。抜いて捨ててしまったら、洋二郎の問いかけを無視することになる。ひいては私自身が生きている意味を失うかもしれない。洋二郎に最近、そう語りかけています。
■絵本の深さ、次男が教えてくれた
――「大人こそ絵本を」と説いておられますが
次男の洋二郎が25歳で天に駆けていってしまってから、何カ月後だったか、ふと立ち寄った駅の書店で、気がついたら児童書のコーナーに悄然(しょうぜん)と立って、懐かしんでいる自分がいました。子どもたちが小さいころ、よく絵本を読み聞かせてやっていたので。
宮沢賢治の童話の絵本が並んでいて、手にとってめくると、自分が少年だったころに揺り戻されたような感覚に陥って、思わず数冊買っちゃった。それから子どもたちに読んだ本を彼の部屋から引っぱり出して読み、新しい作品も買って読むようになりました。
息子の死のトラウマを抱えて読んだから、読み方がまるで違った。絵本って、こんなに深いことを語っていたのかと。やさしい言葉で人生の本質的なことをきちんと表現している。大発見でした。1999年6月に大阪府高槻市で、「読むことは生きること」と題して講演したのが始まり。
さらに「文芸春秋」に「いま、大人が読むべき絵本」と題して書いたら、大きな反響がありました。
――スーザン・バーレイの「わすれられないおくりもの」の話が書いてありましたね。皆に慕われたアナグマが死んでしまうけれど、野原の仲間はそれぞれアナグマからゆたかな贈りものを受けとっていて、心の中で生きていることに気づく、というお話です
6歳の少年が、この絵本を医師に読んでもらい、弟の死をしっかりと受けとめた、という実話に、一番反響がありました。掲載誌を心理学者の河合隼雄さんに送ったら、すぐに「来年、小樽で児童文学のシンポジウムをするから出てよ」と連絡があって。連鎖反応のように輪が広がっていきました。バブルが崩壊した後で、効率主義が徹底して人の心がぎすぎすしていた。「本当に大切なものは何か、生きるって何だろうか、絵本を座右に置こう」と一人キャンペーンのような形で始めたら、次々にキャッチフレーズが浮かんで。「絵本は人生の心の友」、「絵本は人生に三度」、つまり子どものころ、子育てのころ、そして人生の後半にまた読もう、とか。東京の荒川区長が賛同して、区長室前の廊下に絵本コーナーをつくった。絵本を読んだ感想を柳田さんに書こうという「柳田邦男絵本大賞」も始まって、毎年数百通の感想の手紙が届きます。
――洋二郎さんは亡くなる前、柳田さんの57歳の誕生日に、サンテグジュペリの「星の王子さま」の特装版をプレゼントしてくれたそうですね
「おやじ、装丁も挿絵もきれいだから」と。誕生日はいつも花でしたが、その年は違った。僕は飛行機の話が好きだから、サンテグジュペリは好きでしたが、「星の王子さま」は子ども向けの話だと思い込んでいた。2カ月後に洋二郎が自死してから読み返したら、「かんじんなことは目に見えないんだよ」という言葉などに、こんなすごいことが書いてあったのかと。息子は遺言のつもりではなかったと思うけれど、結果的に僕への啓示になりました。
■2.5人称の視点でいのちを見る
――禁酒しているそうですが
この3年くらい、意識的に酒を断っています。2005年に、水俣病に関する環境大臣懇談会委員と日本航空の安全体制立て直しのアドバイザーになり、09年からは、JR福知山線脱線事故調査に関する運輸安全委員会の検証会議委員に。これと並行して、遺族とJR西日本が向き合った安全問題の課題検討会で、助言する役。すべていのちに関わる問題。自分を律し徹夜続きに耐えるために禁酒しました。
――この9月まで、福島第一原発事故の政府事故調の委員長代理をしました。さらに「文芸春秋」で「私の『最終報告書』」を連載していますが、どうしてですか
専門家の視点、行政の視点だけだと、落とし穴ができる。被災した人の側から見ると、穴がよく見えます。被害者の視点から見て、この事故はどのようなものだったのか、全容を語れるようにしたいのです。
――「2.5人称の視点」という言い方もしています
次男の洋二郎が自死を図って脳死状態になったとき、葛藤しました。それまで脳死は人の死だと理解したつもりだったのに、目の前にいるのは死体じゃないっていう感覚が強烈にあって。ひげが伸びるし、洋二郎と魂の対話をしている。この二律背反の葛藤をどう解決したらよいのかと……。
哲学者ジャン・ケレビッチの本を読んで、死には人称性があることを知りました。そのヒントから私は、「私=一人称の死」「あなた=二人称の死」「彼・彼女=三人称の死」、それぞれの深い意味の違いに気づいたのです。いのちをどこから見ているのかということ。その解き口がわかったとき、終末期医療や喪失感の問題を清明に整理できたのです。医療者と患者を考えると、単なる他人の三人称とは違い、人生にかかわる関係がある。しかし感情移入しすぎると客観性が保てない。
冷たい専門家の視点ではなく、客観性を保ちつつ、患者が自分なりの人生を選択し納得できる日々を送れるように寄り添う。そのキーワードとして「2.5人称の視点」を考えました。さまざまな専門的職業人に共通の課題です。これが、僕が半世紀、現場を歩いたなかから、専門化社会に人間性を取り戻す道として見いだした自分なりの思想、到達点です。
――講演で「悲しみこそ真の人生の始まり」と語っていますね
僕が少年のころに父や兄が亡くなり家庭が非常に貧しくなった。ある意味で悲しい時代ですが、そのおかげで、大切なことに気づいた。親のない子の気持ち、旅立つ者が残すべきもの……。人間って、喪失体験をしたり、厳しい局面にぶつかったりすることによって、心が耕され、成熟していく。同時進行では気づかなくても、時間をおくと見えてくる。悲しい体験のポジティブな側面に日頃からもっと気づくことが生き直す力につながるんじゃないかと思って、最近よく話しています。(聞き手 編集委員・河原理子)
◇
やなぎだ・くにお 1936年栃木県生まれ。NHK記者時代に「マッハの恐怖」で大宅壮一ノンフィクション賞。「犠牲 わが息子・脳死の11日」などで菊池寛賞。7月まで政府の福島原発事故調査・検証委員会の委員長代理。
http://digital.asahi.com/
articles/TKY201210250378.html

BACK
〈人生の贈りもの〉柳田邦男(76)(2012/10/29朝日新聞)
ノンフィクション作家
■心を無に、自分の足で現場に立つ
――群馬県の御巣鷹の尾根で、8月の慰霊登山の日にお会いしました。1985年に日航ジャンボ機がここに墜落して、27年。なぜ毎年のように登るのですか?
現場は大事な学びの場。70歳過ぎても足を運びます。特に2005年に日本航空の安全アドバイザリーグループの座長を引き受けてから、安全を考える原点として、たえず自分の足で現場に立ってみないといけないと、自分に義務化しました。
――何を感じましたか
ご遺族が、80代になっても切なる思いで登ってくる。子どもだった人が親になり、幼い子を連れて来る。ここ数年はゆるやかな連携ができて、鉄道事故など他の事故の遺族たちも登ってくる。かつてはそれぞれ孤立して、ひそかに耐えるほかなかったのです。登山者の書く短冊に、今年は原発事故の避難者のものもありました。多くの犠牲者の現場として、歳月とともに重みを増して、根源的なものに気づかせてくれます。けれども僕は、登るときは何も考えません。心を真っ白にして、吸収します。
――なぜですか
わけ知りになっちゃいかんと思うのです。航空機事故や事故調査に関して経験を積んできたとしても、取材するとき、とりわけ被害者を取材するときは、急いだり、「被害者とはこういうもの」という枠組みを描いて質問したりしないほうがいい。現場も、漫然と見ていると感動しなくなる。心を無にしていると、アッと気付くものが目や耳に入ってきます。
――ジャーナリストではなく、ノンフィクション作家を名のっておられますね
ジャーナリストというと、戦場を駆けたり潜行取材して告発したりというイメージがあり、脂ぎっているというか。僕はおっとり型で、そういうたくましさがないので、こそばゆいのです。自分の役割は、事実や原因分析を示すだけではなく、人が生きる物語として、その意味を問うことだと思っています。
「人間は物語らないとわからない」というのは心理学者の河合隼雄さんの言葉ですが、人間は、偶然やちぐはぐさのなかで生きていて、科学や論理性だけでは説明できません。作家とは創(つく)る者。あくまで事実に根ざしながら、僕のみつめた文脈をもとに人間の物語を立ち上げたいのです。事故でも医療でも、かかわった人がなぜそういう判断をしたのか、根源にある生い立ちや人格形成に限りない興味があります。
■「なんとかなるべさ」母に学んだ
――絵本についてのエッセー集「雨の降る日は考える日にしよう」のあとがきに、好きな時間は〈朝は、台所に立って、私が野菜を洗って、朝食のサラダをつくり……夜は、ひとり静かに新たに見つけた絵本をゆっくりと声に出して読む時〉と書いておられます。しかし現実は、猛烈に忙しいのでは?
朝起きたら、といっても夜明けまで原稿を書いて3時間くらいしか寝ないから、ぼけっとしているわけです。ヒゲをそると半分目が覚めて、台所で野菜を6、7種類洗って、サラダを食べるとようやく正気に戻る。家族のサラダをつくるのが僕の目覚ましなんです。野菜と果物をとるのが子どものころからの習慣で、今でもトマトやきゅうりが大好きです。
――いまの栃木県鹿沼市の生まれですね
当時は田舎町で、家の前は田んぼ。借家でしたが50坪ほど畑があって、母が農家の出で、野菜をつくっていたのです。戦中戦後の食糧難の時代も、野菜や芋だけは苦労しなかった。腹が減るとトマトやきゅうりをもいで食べる。食事で残ったイワシの骨を、自分でフライパンでしゃらしゃら焦がすと、おやつができる。それは最高でした。飽食時代の今よりはるかに健康的な食生活でしたね。人生の贈りものの第一は、母が畑をつくっていたこと。一緒に芋を掘ったり、トウモロコシをもいで焼いたり。腹が減ったら自分で用意することも身につきました。もう一つの贈りものは、勉強しなくてよかったこと。
――お父さんは教育者では?
おやじは僕の通った鹿沼東小学校の校長でしたが、肺結核で苦労して、僕が入るころは、とうに辞めて家で療養していました。だから健康が第一。勉強なんかで夜更かしするなって、夜9時には電気が消されました。僕は6人きょうだいの末っ子ですが、旧制中学に通っていた次兄の俊男は、布団にもぐって懐中電灯の光でこっそり勉強していました。僕は高校に入るまで、本は読んだけれど、勉強はしたことない。とにかくよく遊びましたね。麦畑で隠れん坊。ラジオで落語と音楽とか。冬は竹馬を作って雪中行進。
――お母さんは、どんな人でしたか
彫刻家の佐藤忠良さんの「母の顔」という頭像を見た時、親近感を覚えました。印象が重なるのです。佐藤さんも父親を早く亡くして、北海道の夕張でお母さんが働いた。僕の父は敗戦の翌年亡くなりましたが、41歳だった母はパニックも起こさず落ち込みもせず、「どんなに悲しいことがあっても、生きる者は食べなくっちゃね」と言いました。淡々と受けいれて、手内職や畑仕事をした。「なんとかなるべさ」というのが母の口癖。逆境にあってもまじめにこつこつやっていれば、いつか少しましな生活が来るという人生観です。穏やかで、陰口を言わず、子どもたちにも差を付けず、ちゃんと生きていれば「たいしたもんだ」とほめました。僕はマザコンではないけれど、いつのまにか母親そっくりになりました。
■戦争・父の臨終 死見つめた少年期
――小学校、当時の国民学校の3年生まで、戦争中でした
東京大空襲のときは、南の空が赤く焦がされていて、朝まで消えなかった。それから、B29が今の群馬県太田市にある中島飛行機の工場を爆撃して、鹿沼の上空を通って帰っていくようになりました。離れているのに、爆撃音がずしーんずしーんと響く。夏が来るころには、鹿沼でもグラマン機が超低空飛行で機銃掃射して、近所で女の子が撃ち抜かれたのです。一番恐ろしかったのは、夜の焼夷(しょうい)弾爆撃。ごうごうと音が聞こえて、突然、照明弾でぱーっと明るくなって、後続機が焼夷弾を落としていく。大輪の花火が100発くらい一斉に炸裂(さくれつ)したよう。庭先の防空壕(ごう)に潜りましたが、外をのぞいて震えました。一方で、僕は絵を描くのが好きだったから、学校で戦闘機の絵を描いて遊んでいました。
――大きくなったら兵隊に、と思いませんでしたか?
全然、思いませんでした。長兄の芳男が兵隊にとられるときも、鹿沼駅で旗をふって送ったのですが、無性に泣きました。僕は涙もろくて臆病で、突撃精神なんてまるでなかった。大人になって兵隊にとられることが怖かった。けれど、子どものころに戦争を体験したことも、大切な贈りものだと思うのです。戦争の怖さが体にしみつきました。
――戦争の終わりは、どこで知りましたか
8月15日、縁側に家族が集まりラジオを聴きました。僕は意味がわかりませんでしたが、「負けたんだ」と次兄が言ったのです。
――生活の変化は、むしろ次の年にお父さんを亡くしてから?
そうですね。仙台工専(現・東北大学)の学生だった次兄が仙台大空襲の時、雨の中を逃げ惑ったことから肋膜(ろくまく)炎になり、半年後の1946年2月に急逝。その約半年後の7月に父が亡くなりました。父は結核を患い、戦争中は、薬もないので家で安静にして、医者が往診に来るくらい。父の命は長くないんだと感じていました。
7月22日の朝、長兄から順番に枕元に呼ばれました。「健康が第一だ、体に気をつけろよ」と父は僕の手を握り、慈愛に満ちた目でみつめてくれました。その表情は忘れません。父は意識が薄れ、往診の医者が「ご臨終です」と。母が死に水の取り方を教えてくれて、きょうだいで順に父の唇を湿らせ、手を合わせて、お別れしました。生老病死の自然な流れのなかで静かに旅立った。僕が10歳のときのことですが、その体験は最高の人生の贈りものでした。死をおどろおどろしいものとしてとらえなくなった。僕の死生観に、決定的な影響を与えました。
■雲に魅せられ、測候技手が夢
――この夏、長野県・安曇野の絵本美術館「森のおうち」で、パートナーである絵本作家いせひでこさんの原画展と一緒に、初めて雲の写真展をなさいました。夕焼け雲の写真に宮沢賢治の詩「春と修羅」を添え、羊雲の写真には立原道造の「雲の祭日」……。この30年余り、ひそかに雲を撮り続けてきたのだとか
雲を見ていると、詩が浮かんだり、小学校のころのオルガンの音が聞こえてきたりするのです。子どものころは気象台の測候技手になりたかった。小学3年で敗戦。それからは夜空がきれいだったから、風呂あがりに、冬以外はパンツ一丁で、星座を探しました。家に竹針の蓄音機があって、ベートーベンの「運命」や「田園」を聴いて感動して。雑音がすごいんだけど、頭に浮かぶのはそのころの音。ノイズの中から自分の聴きたい音を拾って聴いたから、耳に刻まれたんですね。あとはラジオのクラシックアワー。
――天文や気象は、いつごろ好きになったのですか
父が亡くなって、長兄が父の蔵書を元手に古書店を開きました。僕は小中学生のころ、店番しながら少年科学雑誌を読んだのです。「これからは科学だ」と言われた時代。でも、星はいつ見てもあまり変わらない。次第に雲が好きになりました。それに中学の国語教科書に、ヘルマン・ヘッセの「青春彷徨(ほうこう)」の「広い世界に、私以上に雲を知り、雲を愛する者があったら教えてもらいたい。
世界に雲より美しいものがあったら見せてもらいたい」というあの一節が載って。仲間と授業中でも「おい」「おお、すげえな」と突っつきあって、雲をながめていました。田舎だし、テレビもないし、心がいつも空っぽだから、あらゆるものが魅力的だった。外を歩くと雲を見るのは、中学時代から体にしみついた目線の動きなんです。中3で宮城県の松島に修学旅行に行くまで、海を見たこともありませんでした。あれは衝撃でしたね。世界は広いんだって。
――気象の世界にあこがれたのに、なぜ東大経済学部に
「勉強より健康」だった父親が亡くなって、きょうだいのなかで僕だけ大学へ行きました。母親は「ああ、そうけ」と言っただけ。家にお金がなかったから、高校も行くつもりがなかったのですが、母子福祉奨学金をもらえた。高校時代の友達が「世の中の構造を理解するには経済学が一番いい」と、しきりに言っていた。僕は1年間、塾を開いて学費をためて、1956年に大学へ行きました。マルクス経済学をやったのだけど、ハンガリー事件があってソ連の正体が見えてきた。自分で現場を見て自分の思想と世界観をつくらないと流されるだけだ、と思うようになったのです。資本主義か社会主義か、戦争か平和か、みたいな二者択一の政治論が支配的でしたが、違和感を持ちました。人が生きる社会は、もっと個別性があって、白か黒かではないんじゃないか。社会と人間の真実を見るには記者になるといいと思ったのです。
■現場取材の礎、広島で学んだ
――1960年にNHKの記者になりました。初任地が広島
高校1年のとき、「原爆被害の初公開」を特集したアサヒグラフ52年8月6日号を買って、黒こげの死体やケロイドなどの写真を見て衝撃を受けました。占領下で原爆被害の報道は禁じられていたから、詳しい報道は、このアサヒグラフが初めて。僕はそれを見て、原爆とはこんなにも凄惨(せいさん)な殺戮(さつりく)なのかと、目を開かされました。まさか自分がそこに行くとは……。
――駆け出し記者の生活は?
研修の後、5月17日の朝、広島に着きました。職場にあいさつに行ったら、夕方、バスが田んぼに転落する事故が起きて。デンスケというでっかい録音機を持たされて「とにかく行ってこい」と。それが初取材です。着いたらもう誰もいない。離れた農家まで歩いて行って、現場付近の田んぼの持ち主を聞いたら、ご本人で、しかも事故を目撃していた。そのとき何となく面白いというか、地道に歩いて人に会えば何かに出会うんだ、これが取材なんだと思いました。
――記者3年目の62年、「世界」9月号に、山田国男というペンネームで、「十七年目の広島」を書いています
僕の先輩が、よく寄稿していた朝日新聞の記者と親しくなって、「柳田君、書いてみたら」と声をかけてくれたのです。
――アメリカが核実験再開を決め、広島では34歳の若い警察官が、彼は少年警察官として救援のために市内に入って残留放射能で被爆したのですが、16年たって白血病で死亡した。そうした現実を書いた優れた報告なのに、なぜペンネームだったのですか
まだ駆け出しだったし、NHKは外部に個人で書くことにうるさかったから。僕はアサヒグラフに啓発されたわけですが、それで学生時代に議論したのは政治論や国家論。広島の地に立ち被爆者それぞれの人生に触れて、被爆の現実から核の時代を見る、そういう目を持つようになりました。
現場から見る、被害者から見るという、僕の半世紀の取材の原点が、広島にいた3年半で、与えられたのです。実は、原爆問題取材を始めたころ、失敗をしたのです。3歳の子を残して急性白血病のため27歳で亡くなった瀬戸奈々子さんの日記「かえらぬ鶴」の英訳ができたと記者クラブで発表がありました。瀬戸さんは13歳のときに被爆。しかし、一人の悲劇に秘められた時代への警鐘と普遍的な意味がまだよくわからなくて、記事にせず、特オチ。他社はみな報道しました。深い学びでした。
――雑誌に書いたことは、番組ではできなかったのですか
日々のニュース原稿は、短くしないといけないし、放送はどんどん消えていく。フラストレーションでした。深く取材すればするほど、ニュースには入りきらない。少しでも真実に迫りたいから記者になった。雑誌など長いものを書く方が自分に合う、とそのとき思いました。ちゃんと文章で書く世界で自分は生きたいのだという思いが、うごめき始めたのです。(聞き手 河原理子・編集委員)
◇
やなぎだ・くにお 1936年栃木県生まれ。NHK記者時代に「マッハの恐怖」で大宅壮一ノンフィクション賞。「犠牲 わが息子・脳死の11日」などで菊池寛賞。7月まで政府の福島原発事故調査・検証委員会の委員長代理。
http://digital.asahi.com/
articles/TKY201210180398.html

BACK |