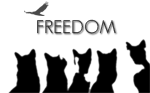| <森村 誠一> |
ウィキペディアより 森村 誠一(もりむら せいいち、1933年1月2日- )は、日本の小説家・作家。推理小説、時代小説、ノンフィクションなどを手がける。山岳を舞台とした作品や[要出典]ホテルを舞台にしたミステリを多く発表している。・・・埼玉県熊谷市出身。12歳にして、日本で最後の空襲となった熊谷空襲を体験。のちの「反戦平和」の原体験となる。 埼玉県立熊谷商業高等学校卒業後、伯父の紹介で都内の自動車部品会社に勤めるが、商品を輸送中に神田駿河台の坂を車が登れず困っていたところを明治大学生に助けられ、大学生になるのもよいと考え、青山学院大学文学部英米文学科に進学。在学中はハイキング部に所属し、山歩きに熱中した。・・・推理小説のシリーズキャラクターとして、棟居弘一良(棟居刑事シリーズ)、牛尾正直(終着駅シリーズ)を生み出している。1977年に映画化された『人間の証明』を中心とした、角川書店の角川春樹社長のブロックバスター戦略の存在の一人となり[要出典]、作品は大半が文庫化され、一躍、ベストセラー作家になった。なお、『人間の証明』は映画化を前提に、角川から依頼されて執筆したもの。その際、角川から「あなたにとって作家の証明となる作品を」と言われたことや、“しょうめい”という音の響きを森村が気に入ったことが題名の由来である。 2015年、平和安全法制成立や改憲を進める安倍晋三政権について、「再び戦争可能な国家にしようとしているが、絶対にいけない。」と批判。また、「組織や権力に庇護されている人間と異なり、国民は自弁というハンディキャップを背負いながら闘っている」と述べた。 森村誠一公式サイト/森村ワールドにようこそ
【言わねばならないこと】(17)民主主義を壊す軸 作家・森村誠一氏(2014年3月16日東京新聞) 民主主義はもろく、いったん壊れると、回復するのは難しい。このまま改憲や解釈改憲まで暴走すれば、安倍首相は不朽の汚名を残すのではないか。政権が進める中国包囲網も軍拡競争を誘発するだけだ。靖国参拝にしても、中韓両国に塩を送る(日本批判の材料を与える)結果になった。戦争もなく、安らかに英霊を守っているのは、多大なる戦争の犠牲の上にできた不戦の誓いである憲法九条であって、中国包囲網ではない。
歴史は繰り返すことを戦争から学んでいない。法成立間際に、官僚が官僚の秘密指定の妥当性をチェックする機関を粗製乱造したのを見ても、いかに秘密保護法の作成、強行成立の過程が杜撰(ずさん)だったか分かる。こういう法律ができたことを国民が忘れず、廃止に向け声を上げ続けることが大切だ。
(天声人語)90歳の原口さんに再審決定(2017年7月1日朝日新聞) 1979年に鹿児島県で男性の変死体が見つかった「大崎事件」である。殺人と死体遺棄の罪で10年の懲役に服した原口アヤ子さん(90)の裁判をやり直すべきだとの判断が、鹿児島地裁から出た▼原口さんは取調室でも法廷でも犯行を認めていない。物証もなかったが、共犯とされた夫らの自白に頼って起訴され、有罪となった。その自白もいまや「捜査機関に誘導された疑いがある」とされ、信頼性が揺らぐ。 殺人事件だったかどうかも怪しくなった▼「あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない」。検察の心構えを示す「検察の理念」の一節だ。そんな当然のことが守られなかった歴史が悔やまれる▼かつて原口さんが口にした言葉が紙面にあった。「逮捕されて以降、心から笑ったことは一度もない」。無実を訴え続けた38年間は、あまりに重い。
愛知)「731部隊」歌い継ぐ 加害の歴史継ぐ(2017年6月24日朝日新聞) 森村さんが原詩を書き、池辺晋一郎さんが作曲した。「私はロシア人親子マルタ(実験材料)を殺した ああ あの時 あの子の澄んだ瞳…… 悔やんでも 流す涙は届かない」。歌詞には、毒ガス実験の被験者にされた母が子をかばう様子など残酷な描写もある。終盤は「過ちを隠せば いつか同じ過ち 悲惨な記憶が風化していく」と、永遠の平和を誓って歌い上げる。
「人に言えない過去、誰にでもある」 ドラマ「人間の証明」棟居役に藤原竜也(2017年3月11日朝日新聞) ・・・棟居と八杉はともに悲しい過去を抱えていた。「誰にでも、絶対人に言えない過去がある。でもそれを断ち切って今の平穏を保とうとする。そこをうまくついている作品だと思う」映画では故松田優作が、ドラマでは石黒賢や渡辺謙、竹野内豊らが演じた棟居。
「社会派」の使命背負い 震災を題材にミステリー 森村 誠一さん(作家)(2014年5月24日東京新聞) 食い物にするのかとね。実際、そういう人と区別がつかないでしょうから。でもね、後になるときっと、感想は変わってきますよ。きちんと書けばね。よく残してくださったと。多くの人の記憶に残すのは、作品にするのが一番ですから」 ・・・こうした強い思いの源流は、十代のころの戦争体験にある。一九四五年八月十五日未明、終戦直前の空襲で自宅や周辺が破壊された。「近くの川に死体が累々としていた。知った顔もずいぶんいました」。壊れずに残った井戸のポンプで水を汲(く)み、空襲で焼けた畑のカボチャを食べた。 「がれきを組み合わせてバラックをつくりました。生存だけを目指す状態ですね。それでも一晩たつごとにね、焼け跡に明かりが増えていくんです。すごいもんだなぁと思いました」。どんなに生活が破壊されても、人はすごい勢いでそれを取り戻していく。そして「生存」から「生活」へと感覚の重心が移ったとき、文学や芸術は必ず求められる。「だから無力だなんて悩む必要がない。私はそう思います」
|