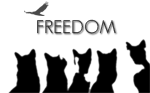司馬 遼太郎(しば りょうたろう、1923年(大正12年)8月7日 - 1996年(平成8年)2月12日)は、日本の小説家、ノンフィクション作家、評論家。本名、福田 定一(ふくだ ていいち)。大阪府大阪市生まれ。筆名の由来は「司馬遷に遼(はるか)に及ばざる日本の者(故に太郎)」から来ている。産経新聞社記者として在職中に、『梟の城』で直木賞を受賞。歴史小説に新風を送る。代表作に『竜馬がゆく』『燃えよ剣』『国盗り物語』『坂の上の雲』など多くがあり、戦国・幕末・明治を扱った作品が多い。『街道をゆく』をはじめとする多数のエッセイなどでも活発な文明批評を行った。
http://ja.wikipedia.org/wiki/司馬遼太郎

BACK
『二十一世紀に生きる君たちへ』(にじゅういっせいきにいきるきみたちへ)は、司馬遼太郎の随筆。司馬が子供向けに書いた初の随筆で、大阪書籍「小学国語」に書き下ろしたもの。「一編の小説を書くより苦労した」と語っている。なお、掲載紙によっては『21世紀に生きる君たちへ』と数字で記されている場合もある。歴史小説家の司馬遼太郎が初めて子供、特に小学生程度の年齢層を意識して書いた文章である。
文章は大阪書籍の『小学国語』(6年生、下)に収録された。なお、この教科書は当時大型書店を中心に市販されている。短いエッセイではあるが、これまで大人向けで歯ごたえのある小説・エッセイを書いてきた司馬だけに、初めて子供向けに書いたという話題性と、その無駄のない文章から、多くの人に読まれた文章である。文を読む限り、司馬自身、自分が生きたまま21世紀を迎えられないことを予期していたと見られ、それを前提に、やがて21世紀を担っていくであろう子供たちに向けての力強いメッセージと羨望の念が込められているこの文章は、まさしく司馬が残した遺書とも言うべきものであるといえる。「司馬遼太郎さんを送る会」でも朗読された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/二十一世紀に生きる君たちへ

BACK
「21世紀に生きる子供たちへ」 (全文)
私は歴史小説を書いてきた。
もともと歴史が好きなのである。両親を愛するようにして、歴史を愛している。
歴史とは何でしょう、と聞かれるとき、
「それは、大きな世界です。かつて存在した何億という人生がそこにつめこまれている世界なのです。」
と、答えることにしている。
私には、幸い、この世にたくさんのすばらしい友人がいる。
歴史の中にもいる。そこには、この世では求めがたいほどにすばらしい人たちがいて、私の日常を、はげましたり、なぐさめたりしてくれているのである。
だから、私は少なくとも2千年以上の時間の中を、生きているようなものだと思っている。この楽しさは、───もし君たちさえそう望むなら───おすそ分けしてあげたいほどである。
ただ、さびしく思うことがある。
私が持っていなくて、君たちだけが持っている大きなものがある。未来というものである。
私の人生は、すでに持ち時間が少ない。例えば、21世紀というものを見ることができないに違いない。
君たちは、ちがう。
21世紀をたっぷり見ることができるばかりか、そのかがやかしいにない手でもある。
もし「未来」という町角で、私が君たちをよびとめることができたら、どんなにいいだろう。
「田中君、ちょっとうかがいますが、あなたが今歩いている21世紀とは、どんな世の中でしょう。」
そのように質問して、君たちに教えてもらいたいのだが、ただ残念にも、その「未来」という町角には、私はもういない。
だから、君たちと話ができるのは、今のうちだということである。
もっとも、私には21世紀のことなど、とても予測できない。
ただ、私に言えることがある。それは、歴史から学んだ人間の生き方の基本的なことどもである。
昔も今も、また未来においても変わらないことがある。そこに空気と水、それに土などという自然があって、人間や他の動植物、さらには微生物にいたるまでが、それに依存しつつ生きているということである。
自然こそ不変の価値なのである。なぜならば、人間は空気を吸うことなく生きることができないし、水分をとることがなければ、かわいて死んでしまう。
さて、自然という「不変のもの」を基準に置いて、人間のことを考えてみたい。
人間は───繰り返すようだが───自然によって生かされてきた。古代でも中世でも自然こそ神々であるとした。このことは、少しも誤っていないのである。歴史の中の人々は、自然をおそれ、その力をあがめ、自分たちの上にあるものとして身をつつしんできた。
この態度は、近代や現代に入って少しゆらいだ。
───人間こそ、いちばんえらい存在だ。
という、思い上がった考えが頭をもたげた。20世紀という現代は、ある意味では、自然へのおそれがうすくなった時代といってもいい。
同時に、人間は決しておろかではない。思いあがるということとはおよそ逆のことも、あわせ考えた。つまり、私ども人間とは自然の一部にすぎない、というすなおな考えである。
このことは、古代の賢者も考えたし、また19世紀の医学もそのように考えた。ある意味では、平凡な事実にすぎないこのことを、20世紀の科学は、科学の事実として、人々の前にくりひろげてみせた。
20世紀末の人間たちは、このことを知ることによって、古代や中世に神をおそれたように、再び自然をおそれるようになった。
おそらく、自然に対しいばりかえっていた時代は、21世紀に近づくにつれて、終わっていくにちがいない。
「人間は自分で生きているのではなく、大きな存在によって生かされている。」
と、中世の人々は、ヨーロッパにおいても東洋においても、そのようにへりくだって考えていた。
この考えは、近代に入ってゆらいだとはいえ、右に述べたように近ごろ再び、人間たちはこのよき思想を取りもどしつつあるように思われる。
この自然へのすなおな態度こそ、21世紀への希望であり、君たちへの期待でもある。そういうすなおさを君たちが持ち、その気分をひろめてほしいのである。
そうなれば、21世紀の人間はよりいっそう自然を尊敬することになるだろう。そして、自然の一部である人間どうしについても、前世紀にもまして尊敬しあうようになるのにちがいない。
そのようになることが、君たちへの私の期待でもある。
さて、君たち自身のことである。
君たちは、いつの時代でもそうであったように、自己を確立せねばならない。
───自分に厳しく、相手にはやさしく。
という自己を。
そして、すなおでかしこい自己を。
21世紀においては、特にそのことが重要である。
21世紀にあっては、科学と技術がもっと発達するだろう。
科学・技術がこう水のように人間をのみこんでしまってはならない。川の水を正しく流すように、君たちのしっかりした自己が科学と技術を支配し、よい方向に持っていってほしいのである。
右において、私は「自己」ということをしきりに言った。自己といっても、自己中心におちいってはならない。
人間は、助け合って生きているのである。
私は、人という文字を見るとき、しばしば感動する。斜めの画がたがいに支え合って、構成されているのである。
そのことでも分かるように、人間は、社会をつくって生きている。社会とは、支え合う仕組みということである。
原始時代の社会は小さかった。家族を中心とした社会だった。それがしだいに大きな社会になり。今は、国家と世界という社会をつくりたがいに助け合いながら生きているのである。
自然物としての人間は、決して孤立して生きられるようにはつくられていない。
このため、助けあう、ということが、人間にとって、大きな道徳になっている。
助け合うという気持ちや行動のもとのもとは、いたわりという感情である。
他人の痛みを感じることと言ってもいい。
やさしさと言いかえてもいい。
「いたわり」
「他人の痛みを感じること」
「やさしさ」
みな似たような言葉である。
この三つの言葉は、もともと一つの根から出ているのである。
根といっても、本能ではない。だから、私たちは訓練をしてそれを身につけねばならないのである。
その訓練とは、簡単なことである。例えば、友達がころぶ。ああ痛かったろうな、と感じる気持ちを、その都度自分中でつくりあげていきさえすればいい。
この根っこの感情が、自己の中でしっかり根づいていけば、他民族へのいたわりという気持ちもわき出てくる。
君たちさえ、そういう自己をつくっていけば、二十一世紀は人類が仲よしで暮らせる時代になるのにちがいない。
鎌倉時代の武士たちは、
「たのもしさ」
ということを、たいせつにしてきた。人間は、いつの時代でもたのもしい人格を持たねばならない。人間というのは、男女とも、たのもしくない人格にみりょくを感じないのである。
もう一度くり返そう。さきに私は自己を確立せよ、と言った。自分に厳しく、相手にはやさしく、とも言った。いたわりという言葉も使った。それらを訓練せよ、とも言った。それらを訓練することで、自己が確立されていくのである。そして、“たのもしい君たち”になっていくのである。
以上のことは、いつの時代になっても、人間が生きていくうえで、欠かすことができない心がまえというものである。
君たち。君たちはつねに晴れあがった空のように、たかだかとした心を持たねばならない。
同時に、ずっしりとたくましい足どりで、大地をふみしめつつ歩かねばならない。
私は、君たちの心の中の最も美しいものを見続けながら、以上のことを書いた。
書き終わって、君たちの未来が、真夏の太陽のようにかがやいているように感じた。
http://gogodiet.net/Forkids.htm

BACK
司馬と池波、先達への敬意 子母沢寛あて礼状見つかる(2013/08/23朝日新聞)
【中村真理子】作家、子母沢寛(しもざわかん=1892〜1968)にあてた、司馬遼太郎(1923〜96)、池波正太郎(1923〜90)の手紙が見つかった。子母沢は手紙のほとんどを処分していたが、くずかごから遺族が取り出し、保管していた。いずれも子母沢から資料を譲られたことへの礼状で、当時の作家たちの温かな交流が伝わってくる。
司馬からの手紙は2通残されていた。64年の手紙は「『薩摩びわと児玉天南』の切りぬきを頂戴(ちょうだい)いたし、うれしさ、感激でいっぱいであります」とあり、「読みながら琵琶の音まできこえてくるような思いでございました」と続く。
67年、子母沢を訪ねた後の司馬の礼状は、「家内から、『奥さまには蘭(らん)をもってゆけ』といわれておりましたのですが、大阪にもよき蘭がなく、東京にもなく、どうにもならず、ついにハダカ身で参上つかまつりました」とユーモアにあふれる。
池波からの手紙は68年4月、「今朝またまた御蔵書をたまわり、しばらくは家内と顔を見合(みあわ)せ、ただもう恐縮いたすばかりでございました」とある。当時、司馬は「竜馬がゆく」、池波は「鬼平犯科帳」で人気の頃。晩年の子母沢は、親子ほど離れた後輩作家に資料を譲っていたようだ。子母沢の「新選組始末記」(28年)は、生き残り隊士からの聞き取りを取り込んで構成した、新選組ものの原点といえる小説。司馬は新選組を書く際、子母沢を訪ねて仁義を切ったというエピソードが残されている。
池波はエッセー「食卓の情景」のなかで「私が〈鬼平犯科帳〉なぞを書いているのを御存知(ごぞんじ)で、関係のある貴重な古書を送ってくだすった」とつづっている。元編集者として3人を知る文芸評論家の大村彦次郎さんは「子母沢さんは文壇のつきあいは少ない方だったが、手紙のやりとりから後輩作家たちから敬意を抱かれていたことがよくわかる」と話す。
http://digital.asahi.com/articles/TKY201308220080.html

BACK |