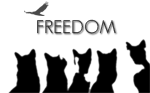| <保坂展人> |
原発という巨大システムとの訣別(2014/01/28朝日新聞)文 保坂展人 たとえば、2013年夏、東京23区内で115人の方が室内で熱中症にかかって亡くなりました。その多くが高齢者で、エアコンがないか、壊れているか、あっても使用してない方でした。(熱中症死亡者の状況)世田谷区でも9人の方が亡くなりました。 そこで、犠牲者を減らすために、ひとり暮らしの高齢者が室内で「熱中症の危険度」を確認できるような配布物を配ったり、猛暑時に涼しい処でみんなですごす「クール・シェア」をすすめたりしています。高度経済成長を経て、成長があたりまえだった時代は終わり、人口減少社会に転じています。地域では高齢化が一層進み、行政への需要が増す一方で財源は限られる、という時代を迎えています。 しかも、かつてあった「家族」のかたちは劇的に変わりました。世田谷区の65歳以上の高齢者のうち「一人暮らし」が約30%(約5万人)、65歳以上の「高齢者のみの世帯(夫婦)」は約36%(約6万人)を占めます。また、世田谷区の行なった全高齢者調査では、一人暮らしの高齢者で家族や親族・友人と連絡する機会が少ない「社会的孤立」の状況にある方が15.7%(男性は29.2%)という結果も出ています。 「おはよう」とか「ただいま」とか、ひと言でも誰かと話すという、あたり前のように思われていることが、心と体の健康のためとても重要であり、そういうことを大切にできる社会にしていかなければならないと思います。そうした時代だからこそ、暮らしの場である地域コミュニティの中で、区民がお互いに助け合い、支えあい、さらに行政がそれを補完するという仕組みをつくろうと考えています。地域の見守りなどの緩やかな福祉サービスをはじめ、住民同士の顔の見える関係を活かした温かな地域コミュニティを再構築することが私たちの課題です。 高齢者福祉も、子育て支援も、大型施設中心の供給型から、地域に密着した小規模の場づくりによる住民参加型へとシフトしてきています。大きなシステムを行政が構築して、住民はそこを選ぶ以外の選択肢がないという社会から、地域の実情にあわせた参加と協働の社会へと変われるかどうかがポイントで、エネルギーの問題もまさに同一です。2011年の東日本大震災と福島第1原子力発電所事故は、私たちに大きな衝撃を与えました。 これまでの社会で常識とされた科学技術に対する「安全」や「信頼」は瓦解し、「原子力ムラ」の論理をふりまわす専門家の権威も失墜しました。「原発はクリーンエネルギー」と旗をふっていた文化人や評論家たちは一時的に声をひそめました。 事故直後のドキュメントを読み直してみると、「全電源喪失」の事態に直面して、国や経済産業省、原子力保安院、原子力安全委員会等がどれだけ判断停止に陥っていたかがわかります。国や専門機関は、深刻な原発事故に遭遇して、あまりに無力でした。にもかかわらず、十分な事故原因の検証もしないまま、国は再稼働を進めようとしています。 閣議決定を目前に控える国のエネルギー基本計画の中で、原発を「基盤となる重要なベース電源」とまで位置づけた経済産業省、そして安倍内閣。底流にあるのは、「原子力規制委員会の審査をパスすれば、3・11は繰り返されないだろう」という、根拠なき楽観主義に思えます。 電力会社もまた、経営のために「再稼働」にしがみつこうとしています。「これから気をつけます。きっと大丈夫ですからやらせて下さい」というのが本音でしょう。福島第1原発事故を起こした東京電力に巨額の融資している銀行団も同じです。かれらの価値軸は、コスト優先の経済効率です。電力会社が財務体質を改善するには、原発を稼働させるのが一番合理的だという考え方です。仮に重大事故のリスクが存在したとしても、「3・11ほどの事故を繰り返す確率は低い」ので検討するには及ばない。 自治体の首長が「メルトダウンなどの重大事故時の避難計画を立てることができない」と指摘しても、「その危険性は低いのだから、とりあえず原発を稼働させながら考えましょう」という感覚です。それは、3・11以前と何も変わっていないことを示しています。事故前、「津波の襲来による電源喪失」を指摘する声に対して、国や原子力保安院、電力会社は「きわめて確率が低いので、想定する必要はなく、リスクとして排除していい」と考えていました。 いま再び、「世界一厳しい審査をクリアすれば、世界一安全な原発になる」として再稼働に突き進もうとしています。次の巨大地震が予想される地震列島で原発を動かすリスクをも、経営の論理が塗りつぶしてしまうのです。原発事故は1度起きてしまったら、制御するのが困難で、放射能汚染が広がれば、人々は長期にわたって住み慣れた故郷を離れるしかなくなるのです。それは福島の原発事故の影響を受けた地域の現実が示している通りです。 私たちは、第2、第3の原発事故の恐怖を抱えながら暮らしたくありません。汚染された山河を元に戻す技術を持っていません。たとえ再稼働したとしても、全国の原発に残されている使用済み核燃料は増えつつけるばかりです。青森県六ケ所村の再処理工場は、トラブル続きでなかなか機能しないだけでなく、故障・事故続きの高速増殖炉もんじゅ(福井県)はガタガタで、巨費を投じてきた「核燃サイクル」の破綻は明らかです。私たちはすでに、途方もない時間と予算を必要とする「負の遺産」を抱えています。ならば早く、原発という未熟な技術に見切りをつけて、いまだに見えてこない核廃棄物の最終処分までの工程(ロードマップ)を描き、人材と技術を「原発の後始末」に集中するべきではないでしょうか。見せかけの経済効率を掲げて原発を再稼働させ、核のゴミを増やしつづけながら、積み残された課題を検討しましょうというのは、問題の先送りにほかなりません。 怠惰と批判されても仕方ないでしょう。解決策の見当たらない宿題を未来の世代に押しつけることこそ、「無責任」ではないでしょうか。人口の集中する都市に住む私たちが、事故の危険がある原子力発電所を福島や新潟などに建てて、当然のように電力の供給を求め、そして消費してきたのが、これまでの社会でした。そうしたあり方を問われたのが3・11だったはずです。私は、日本の近代史にあって、明治維新、第2次世界大戦に続く第3の歴史的転換点である、と考えています。私たちの暮らしに、原発という「巨大システム」を事故リスクとともに押しつけられる社会から引き返すとすれば、今です。 緊張と絶望 孤独の10代を越えた先に(2013/10/01朝日新聞)文 保坂展人 「ぼくは二十歳だった。それが、人の一生でいちばん美しい年齢だなどと誰にも言わせまい」(ポール・ニザン『アデン アラビア』より) 夜中に、長いこと身体の中に潜伏していた10代後半のころの記憶がよみがえり、苦悩と思索と試行錯誤の中にいた「あのとき」が目の前に現れることがあります。人はだれも若かった時代をまばゆいばかりの青春の記憶として飾りたがります。でも、私にとっては、苦しく、暗く、細い回廊を手探りで歩くような時期でした。自分が何者であるのか、自分はどこから来たのか、そしてどこへ向かって歩んでいくのか――。出口のない暗闇の中、ただひたすら考え続けていました。そして、喫茶店の片隅に座っては、2時間も3時間もかけて、なんとか数行の文章をつづるということを繰り返していました。安物のボールペンを握りしめ、筆圧の強い文字を刻みつけるようにノートに書きつけていたのです。 それから40年の月日が流れ、予想もしなかった道を歩むことになりました。この間、「あのとき」を思い出したのはわずかな時間でした。それよりも、今日準備しなければならないことがあり、明日のために仕込まなければいけない仕事がありました。いまも、その只中です。 けれども、50代後半になったからこそ、「あのとき」が問いかけているように感じることがあります。無限に見えた人生の時間の重さを嘲笑するかのようなふるまい。世間を知らないからこその陶酔……。きまりの悪さや後悔を抱えてもいました。「あのとき」、私はひとりでした。ひとりであることを選び、ひとりであることに耐え、自力ではいあがろうともがいているような日々でした。非力を知っているからこそ、自分を鍛えるためにひとりでいようとしていたのかもしれません。 そうした泥沼の中で「思考」は成長し、「言葉」は変容しました。まるで乳歯が永久歯に入れ代わるように、だれかの言葉に代わって自分の言葉らしきものを手に入れることができるようになりました。ボールペンは何本もインクが切れて、大学ノートはやがて何冊にもなりました。20代を過ぎて、私は教育雑誌や月刊誌に文章を書いて原稿料を得る生活に入ります。大きなチャンスを迎えたのは、23歳。当時、四六版だった月刊「宝島」で、いきなり巻頭100ページの特集を書くという依頼を受けたのです。 私は、沖縄民謡の大家の父を持ち、コザ(現沖縄市)に生まれたロックミュージシャンの喜納昌吉さんを訪ね、彼の家に3カ月ほど住み込んで、東京、神戸、宮古島へともに旅をしながらドキュメントをしたためることにしました。書き上げた作品は「魂を起こす旅 喜納昌吉」(「宝島」1979年8月号)として書店に並びました。 このとき、締め切り前の1週間足らずで、400字詰め原稿用紙で300枚を書き上げた記憶があります。5年前には数時間かけても3行しか書けなかった私は、ひとつの言葉を吟味し、文章をつなげては切り離し、そして流れを生みだしてゆくという技術をいつしか身につけていたのです。その後、少年少女向けの芸能誌で10年間、仕事を続けることになりました。 文章だけではありません。衆院議員として永田町に身を置いてからは、借りものではなく、自分の頭で考えるという訓練が生きることになります。政治の世界は、日本でもっとも情報が交錯し、容量を超えた情報が奔流のように流れ去っていきます。その中から脈絡のない点と点をつなぎ、やがて大きな問題となるであろう小さな兆候を見つけだす。 そのうえで調査や分析を加え、国会審議での質問を準備するのです。あたかも激しくうねる大海原にイカリを降ろすかのように、核心を見すえて問い続ける。その力はは確かに、「あのとき」に由来するように思うのです。 そして今、88万人の暮らしを預かる自治体の長としての仕事に向き合っています。取り組まなければならないいくつもの課題のひとつとして、生きにくさを抱える若者たちの支援を考えています。振り返れば、若いころの私は無手勝流に本を読み、深い洞窟に隠れるように多くの時間を過ごしていました。あのときは、それがどこにつながるのかが見えていたわけではありません。 それでも誰かに依存することなく、孤独を抱きしめるようにして自分と向き合ってきた結果、気がつけば、いまにたどりついていたのです。とはいえ、自分の経験を絶対視したり、若者たちに教訓を垂れたりするつもりはありません。 ただ、「あのとき」の緊張感、深い絶望、そして、かすかな希望を仰ぎ見るときの心臓の鼓動を忘れないでいたい、と思っています。 保坂展人(ほさか・のぶと) http://www.asahi.com/and_w/life/TKY201310010063.html
|