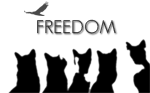高村 薫(たかむら かおる、1953年2月6日 - )は、日本の作家・小説家。女性。本名は林 みどり。 2012年の最新作『冷血』はトルーマン・カポーティの同名作品へのオマージュとされ、さらに深化した世界をみせた。寡作だが、『マークスの山』から続く合田雄一郎シリーズなどで熱狂的なファンを持つ。
(寄稿)精神世界、無関心な私たち 高村薫(2018/07/11朝日新聞) 死刑制度の是非はべつにして、かくも重大な反社会的行為が身近で行われていた数年間、日本社会はいったい何をしていたのだろうか。私たちはオウム真理教の何を恐れ、何を断罪したのだろうか。教祖らの死刑執行を受けてあらためてそんな自問に駆られる傍らには、教団の反社会性を看過し続けた私たちの無力と無関心、さらには一方的なカルト宗教批判に終始したことへの自省や後悔が含まれている。また、教祖らの逮捕から二十三年、日本社会がこの稀有(けう)な事件を十分に言葉にする努力を放棄したままこの日を迎えたことへの絶望も含まれている。 裁判では、宗教教義と犯罪行為の関係性は慎重に排除され、一連の事件はあくまで一般の刑法犯として扱われたが、その結果、神仏や教祖への帰依が反社会的行為に結びつく過程は見えなくなり、宗教の犯罪という側面は手つかずで残された。しかしながら、どんなに異様でも、オウム真理教は紛れもなく宗教である。それがたまたま俗世の事情で犯罪集団と化したのか、それとも教義と信仰に導かれた宗教の犯罪だったのかは、まさにオウム事件の核心部分であったのに、司法も国民もそこを迂回(うかい)してしまったのである。 形骸化が著しい伝統仏教の現状に見られるように、日本人はいまや宗教と正対する意思も言葉ももっていない。この精神世界への無関心は、理性や理念への無関心と表裏一体であり、代わりに戦後の日本人は物質的な消費の欲望で人生を埋めつくした。地道な言葉の積み重ねを失ったそういう社会で、若者たちの求めた精神世界が既存の宗教でなかったのは、いわば当然の結果だったと言える。彼らは伝統仏教の迂遠(うえん)な教義と権威を拒否し、手っ取り早いヨガの身体体験に出会って社会に背を向け、疑似家族的なカルト教団に居場所を求めたのである。・・・ そしてもちろん、信心と帰依は信仰の本態である。また信仰は本来、自身を守るための殉教や殺戮(さつりく)もあり得る絶対不可侵の世界であり、もとより社会制度や通念とは相容(あいい)れないところで立っている。オウムをめぐる言説の多くが生煮えに終わったのは、信仰についてのそうした本質的な認識が私たちに欠けているためであり、自他の存在の途絶に等しい信心の何たるかを、仏教者すら認識していないこの社会の限界だったと言えよう。 それでも、いつの世も人間は生きづらさを和らげる方便としての信仰を求めることを止(や)めはしない。オウム真理教が私たちに教えているのは、非社会的・非理性的存在としての人間と宗教を、社会に正しく配置することの不断の努力の必要である。 「震災・原発・政治・・・作家・高村薫さんに聞く」 報道ステーション 古館 高村薫 「厳しいけれども、そこで人間の理性の出番でね。それはいろいろ問題はあるでしょう。電気がストップすれば経済活動も制限されるますし、不便があります。代替エネルギーと言っても、すぐにどうかなるわけではない。そういういろいろな状況はあるけれど、でも、福島のあの事故の結果の重大さと悲惨さと、そこで被害を受けた方たちのことを考えたときに、ここで一歩踏み出さなかったらいつ踏み出すんだという思いがあります。ダメなものはダメでしょう、ということです。 そんなもの(原発)を日本中で54基も抱えているのは、正気の沙汰ではないと思うのが人間の理性だと思うんですけどね。企業家の方たちはね、“だけど”とおっしゃるんですよ。“現実を見てくれ”と。“企業が生産活動が出来なくなったら困るのはみんなだ”と。だけど私は、企業活動としてではなく、人間として、こんな狭い地震国では無理だと、もうダメだと」 「再稼働の流れが、一部原発の窯にはありますけども」「してはならないと」「分かっちゃったんだから」 「そうです。それに、本当に地震はいつあるか分からない。日本が少しずつでもね、新しい歩みを始めることが出来るのか、あるいは出来ないのか。いま本当に分かれ目だと思います。厳しい現実と厳しい決断をすること、そのことが希望だと私は思う」 「そのこと自体が」 「生き方を考えなきゃいけないんですね、10年20年先を見ながら」 「いい機会だと思います。今年の夏ね、節電でみなさん価値観が変わったのんじゃないかなと思うんですね。東京電力が言うほど、生活者は堪えていなかったと思うんですよ。価値観は私たちが変えていくものですよ。そうすると、企業は後からついてくるんだと思います」「ある人が言ってたんですよ。 税金上げる時にだけ、次世代、次々世代にツケを回すなと言うんだけど、核のゴミなんか10万年先までどうするんだと。次々世代なんてもんじゃないじゃないかと。確かにそういう都合のいい、何ていうんですか、どういう時に次世代を政治家なり仕切る人たちが使うのか、言葉のいやらしさなりレトリックなりってことを見抜くってことは、しんどいけど、私たちの役目かもしれませんね」 「とにかく引っかかったことは覚えておく。違和感を覚えたことは覚えておく。流さない。違和感は違和感として抱えていること。日本人はむしろ逆ですもんね。周りに合わせて合わせて合わせて、何か自分が違うことを言ったら自分がおかしいんじゃないかって。そうやって、みんなでダーッと流されていく、普段の生活はそれでいいんですけど、そうやって“かつて戦争が起こった”と思ったら、やっぱり孤独でも何でも違和感を持っている方がいいと思いますね」 「決断をすることが希望の序章だというお話を伺いました。高村さん個人は、作家として、どういう活動の中に、書くことの中に、希望をこめていかれるんでしょうか?」 「日本の財産といえば自然の風土だと思うんですよね。だから、日本人として生まれて生きて、おそらく多くの方が無意識のうちに帰りたいと思っている、自然とか土とか水とか、そういう物のことを書きたいですね。特にそれは原子力の災害で失われましたからね。本当に草一本、木一本、それが生えてる土地、土、土くれですね。それがどんなに素晴らしいものか」 「ちょっとハッとさせられたのが、まだ失われていないと思いたいから失われていないというふうにちょっとなってる自分がいましたけども、一度失われてしまったからと過去形でおっしゃりましたね」 「私には失われたとしか思えない。セシウムとか他の放射性物質だって、ずっと残るんですよ。人体に影響があろうがなかろうがずっと残る。本来自然界にないものが。私たちが何千年か、先祖の時代から立って生きてきたこの土地、土くれと共に生きる、例えば草であり花であり人間であり、そういうことを言葉にしたいです。早い話が、原子力やめてほしいですけどね」 「感じましたのは、口当たりのいい言葉だけでは何ら意味をなさず、とにかく人間一人一人が、あるいは政治が、あえて苦しいけど覚悟を決める、というふうにした時に、それがイコール希望なんだと。それがない限りはいつまで経っても希望という言葉だけが空しく響くと、お話を伺っていて強く感じました」 NHK ニュースウォッチ9 大越)一進一退が続く福島第一原発。今回の事故は私たちが原子力にどう向き合うべきかを考える上で大きな分岐点になったともいえそうです。これまで原発を題材にした小説を発表し、その脆さや原発を巡る社会のひずみといったものを社会に問いかけてきた大阪在住の作家 高村薫さんにインタビューしました。 ナレ)作家の高村薫さん。25年前のチェルノブイリ原発の事故をきっかけに原発の持つ危うさに関心を持ってきました。チェルノブイリ原発事故の5年後に発表された小説『神の火』。原発の構造を徹底的に取材し、テロや戦争に対して脆弱だと警鐘を鳴らしました。しかし今回、恐れていた事態が津波で引き起こされた意味は重いと考えています。 大越)原発がやられたんだ、と知ったとき、どういうことを考えましたか。 自分が生きている間に こういうことが起きるとは、よもや想像していなかったので、この先も日本が国としての形をちゃんと保って存続していけるのかというそれぐらいの瀬戸際に立たされている、それぐらい大きな事故だと思います。 ナレ)なぜ事故は避けられなかったのか。高村さんは非常用のポンプや電源が屋外に設置され、対策が施されていなかったことに愕然としています。
ナレ)更に高村さんが厳しい視線を送っているのは政治です。
ナレ)高村さんは2005年に発表した著作「新リア王」の中で原発の誘致に携わった政治家に こう発言させています。『電源多様化を名目に わが国では代替エネルギーとしての原発増設に拍車がかかった。疾走する原子力事業に対して政治は時どきに正しい舵取りを成し得たのか否かだが、答えは少々心もとなかったと言わざるをえない。』 この日本の原子力政策が行われてきた半世紀というのは55年体制と同時でしたので、原発の問題が常に賛成か反対かに分かれて、それが常にイデオロギーと一緒にされてきた。それが非常に不幸なことで、私たちは消費者あるいは国民としてイデオロギーや政党色を置いて、技術、まさに科学技術として どのような現実的な評価が行われてきたか。それを知りたいんです。 ナレ)そして事故が起きた今こそ判断に必要なデータがあると指摘しています。 『この地震国で原子力発電をするときのコスト』を もう一度冷静に計算し直してみる必要が絶対にあると思います。たとえば耐震化工事にかかる費用、あるいはこういう事故が起きたときの補償や賠償の費用、その上で私たちが それでも原発を使うのか、それこそ私たちの選択にかかっているんだと思います。 ナレ)最終的な選択を迫られるのは私たち自身だという高村さん。日本のエネルギー政策や暮らしのあり方が問われていると考えています。 私たちが今できるのは 逃れられない現実に耐えて見つめ続けるか、あるいは目をそらして無かったことにするか、逃げるか、なんですね。私は、逃げてはならない、と思います。現実に福島で 生まれ育った土地、仕事も家も子供もある土地を追われて 今日明日にも逃げていかなくてはならない方たちがおられる。それを無かったことにして、時間がたてば元通りになるという根拠はどこにも無い。 大越)これだけのことがあっても 今の豊かな電力供給を原発が担っている以上は 私たちはそれに乗っかって生きていくという道を無意識に選択している人も多いですよね。これまでと同じように生きるという選択肢は無いんだと思っています。
大越)高村さんは「自分は科学技術に対して全面的に信頼を持って育ってきた世代で、科学技術というものを前向きに評価している」ということでした。そこで この震災を機に次世代のエネルギー社会を作るという夢を掲げて一歩抜け出すことを日本は考えるべきではないかと話していました。原発を徹底的に取材して警鐘を鳴らしてきた作家の良心がそう語っているように思いました。 RED STAR'S CLUBあ〜るさん書き起こし
(古典探遊)作家・高村薫が語る「ブラームス」(2013/06/12朝日新聞) 音と音、節と節、楽章と楽章がつくる関係に不用意な箇所が一つもない十全なる構成。ワーグナーのように、あるテーマを表現するために作られた音楽ではなく、音のためにだけ作られた音だ。いかに形式を守ろうとも、天才ゆえに意識と技巧による構造物のまわりで才気がはじけている。ピアノ協奏曲第2番。私もピアノを少し弾くので分かるが、ものすごく難しい曲。 技巧を極めた音が分厚く重ねられ、やがて馬車のように駆け出し、耳をわしづかみにして聴くものをどこかに連れていってしまう。交響曲第2番は、壮大な第1番と比べると、こぢんまりしているけれど、穏やかな明るさに満ちている。長い年月をかけて苦労した第1番と違い、ひと夏で書き上げたというだけに、精神的充足、わき出る創作意欲が感じられる。
小説を書くときに、私が作りたいのも、この空気、この世界だ。ある時代、ある場所を舞台に、AとBがいて……という小説の全部から生まれてくるのが空気。これができれば小説の9割はもう成功している。物語はときがたつと陳腐化するが、この空気は変わらない。ある小説が好きというのは、その小説が持つ空気が好きだということ。そこに快楽の本体がある。 私の小説を書く方法は、ブラームスの音楽によって、つくられたのだと思う。おこがましいけれども、私はブラームスの曲の作り方がよくわかる気がしていて、私の小説の創作方法はそれと似たものになった。あの日の深夜ラジオでの出会いがなければ、今の作家としての私はない。
(寄稿 2013参院選)地に足をつけて 作家・高村薫(2013/07/05朝日新聞) 太田猛彦著「森林飽和」によると、日本人は古来、燃料や肥料や資材として森林資源を利用し続け、江戸時代にようやく保全の取り組みは始まったものの、20世紀初めには国土の6割を占める森林の半分以上を荒廃させていたのだという。近代化に伴う薪炭需要の増大や養蚕業の発展などで日本各地の山の荒廃が史上もっとも進んだ明治時代、殖産興業に憑(つ)かれた人びとの眼にあったのは、崩落で荒れた山肌にそびえる未来のダムや水力発電所の姿だったのだろうか。 都会でつくられるさまざまなブームだけでなく、成長の終わりに伴う経済規模の縮小や衰退も、少子高齢化も、まずは地方に響いてくるのだが、大型トラックが通過したあとの空っぽの中山道を眺めながら、かつてはここを満員のスキーバスが行き交った面影もない、人間の営みの移ろいを思った。都会の人間は里山に憧れる。けれども、戦後造林されたスギ・ヒノキが安価な輸入材に押されて放置され、薪炭需要も減った結果、皮肉にも日本の山々は深い緑を回復したに過ぎない。 前掲書の太田は、森には「使う森」と「護(まも)る森」がなければならないと説くのだが、どちらも危機的状況になっている今日、私たちは深々とした山の緑に新しい荒廃の姿を読み取らなければならないということだろう。とはいえ、これは単純に林業や山村を再興させれば解決する話なのだろうか。私の住む関西では、2011年9月の台風12号の豪雨災害が記憶に新しい。 河川の氾濫(はんらん)と山腹崩壊に伴う土石流やせき止め湖の決壊により、奈良・和歌山・三重の3県で死者・行方不明者88人を数える大災害となったものだが、総雨量が千ミリを超えるような集中豪雨の前では若者も年寄りもない。人工林も自然林もない。 当時紀伊半島で起きた山腹崩壊の一部は、表層ではなく岩盤の深さまで崩れ落ちる深層崩壊だったと言われているが、これまで滅多(めった)に起きないとされてきた種類の崩壊が現実に起きるようになった気候変動の時代に、私たちは生きている。 山を畏(おそ)れ、拝み、ときに山崩れや洪水に押し流されて集落を壊滅させながら、それでもしぶとく再起してきた暮らしがそこここにある、というだけである。だからこそ人びとは、崩れた道路やのり面を何度でも復旧させて暮らしを取り戻そうとするのだし、紀伊半島ではいまなお崩落箇所の復旧工事が続いているのである。 林業の復活には時間がかかる。加えて、もともと厳しい自然条件の下での山間の暮らしである。かの鈴木牧之が「北越雪譜」に描いた江戸時代のそれとは違い、山を下りても別の暮らしがある今日、紀伊山地でも限界集落の増加は止まらない流れとなっている。「使う森」「護る森」はまだしも、「住む森」はいずれ消えてゆく運命にあるのだろう。先の台風被害では和歌山県田辺市の集落が一つ廃村となったが、解散式の様子を撮影したビデオ映像では、村を去る人びとの決意と諦観(ていかん)の表情が印象的だった。 チェルノブイリや福島のように、原発の重大事故で強制的に故郷を追われる人びと。選択の余地もなく故郷を追われるのは、内戦状態のシリアや、ソマリアや南北スーダンなどの難民もそうだろう。限界集落も土砂災害も、原発事故も戦争も、みな人間の営みの過剰と欲望の物語であるが、同時に個人の意思の及びがたい共同体全体の物語でもあり、それゆえどんな離郷も深い無念の光景となる。人が離郷で失うのは、馴(な)れ親しんだ暮らしだけではない。最大の喪失は、土地の匂いといった己が身体に根ざしたアイデンティティーである。 土地の記憶の代わりの星条旗である。もっとも、人が自ら土地を捨てる例は日本にもある。蝦夷地でアイヌの人びとが捕っていたニシンは、江戸時代の松前藩で本格的な漁が始まり、明治大正期にピークを迎えた。ニシン漁の隆盛は多くの漁民を北海道沿岸に引き寄せたが、50年代に突然ニシンが来なくなると、潮が退くように人が去り、集落が消え、鉄道が消え、いまでは何もない草地と閑散とした道路が残されているだけである。 そこでは近隣の田んぼもまた捨てられて草地に返っているが、農耕民族であっても、人は食えなくなった土地をさっさと捨てて移動してゆくものだということである。 ちなみに、いったん人がいなくなった土地自身は、次に人がやってくるときまで自然に返るだけのことである。ところで、「私たちが必要とする限り」と書いたが、私たちはいったい何をどこまで必要としているのだろうか。 「生きるための最低限」ではなく、「できるだけ多く」でもなく、問うべきは一人一人が「どう生きるか」であり、そのために何が必要か、である。いずれ確実に起きるとされる南海トラフ地震について、国はここへ来て発生の予測はできないとする一方、1週間分の食糧備蓄を、と言いだした。予測では、最大死者数が32万人。 被害総額は東日本大震災の10倍の220兆円。東海から九州の太平洋沿岸にかけて、地震発生から数分で高さ20メートル、30メートルの津波が到達するとされる町村が並ぶ。被害の大きさと復興に必要な国力などを考えると、一部の町村は地図から消えてしまうことになるのかもしれない。 話題となったデイビッド・モントゴメリー著の「土の文明史」を読む。人間の農耕文明は土壌に頼るだけでなく、灌漑(かんがい)や鋤(すき)の利用や施肥によって収量を絶えず増大させてきたこと。収量が増えると人口も増え、それがまた農地を拡大させてゆくこと。その営みが必然的に土壌を使い果たし、やがては一つの文明の終焉(しゅうえん)をもたらしてゆくこと。 著者は、富のためであれ、生きるためであれ、人間が知恵を駆使してこの大地で生きること自体が不可避的にもたらす文明の限界を見据えているようだが、そうは言われても――と思う。
その一方、もともと土壌が痩せている熱帯の原野を、食糧確保のために先進国がこぞって大豆畑に変えるような醜い収奪を拒否する理性も求められるだろうし、40万ヘクタールもの国内の耕作放棄地や減反政策を解消するための、今日明日の努力も求められるはずだ。 躍る言葉に背を向け、文字通り、地に足をつけることである。明日にも大地震や豪雨に呑(の)み込まれるかもしれないこの大地と、是も非もなく向き合うとき、初めて「どう生きるか」という意思と選択の問いが始まる。いまこそ、そういう日本人でありたいと思う。 |