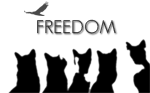1948年東京生まれ。画家。スペイン在住。『武満徹全集』の装画で経産大臣賞、「世界で一番美しい本」展(独ライプチヒ)日本代表。全日空機内誌の表紙画も手がける。近年は陶芸も。近著に絵本「大渦巻」(架空社)。 [アート特派員]真実のフラメンコ/堀越千秋@マドリード(2013/09/15GLOBE朝日新聞) フラメンコと闘牛には共通点がある。どっちも「オレ!」とかけ声をかける。「オレ」とは、もともとアラビア語の「アラー」である。「神」だ。 さて、フラメンコというのは、スペインでは、常識として、歌(カンテ)のことだ。踊りはバイレという別物である。日本人は、フラメンコというとあの「情熱の踊り」をイメージしてしまう。しかし、それは民謡の盆踊りのようなもので、ほんの一部でしかない。フラメンコの本場アンダルシア地方では、真夏の夜に、各町村で「納涼フラメンコ大会」が催される。 校庭や闘牛場に舞台をつくり、イスを並べて、数百から千人単位の町民、村人が家族連れで集まって、夜11時ごろから始まる。出演者はプロの歌い手たち、カンタオールだ。おおむね10人ほどが順番に、ギターの伴奏で明け方まで歌ってゆく。踊りは、ない。せいぜい中入りの息抜きに1人だけ。あるいは、速い曲のラストに歌い手の興がのって、自らイスから立ち上がって踊り出すか。 今は亡き、天才カンタオール、テレモート・デ・ヘレスが、ロンダのフェスティバルのラストで、快速調のブレリアのリズムにのって立ち上がり、軽く両腕を上げて、すっすっと小粋なひとふりを見せたとき、観客は皆口を開いて喜び、「オレ!」と叫んだ。ほんの10秒に満たない、こうした瞬間にこそ、「渋」が醸しだされる。 ひょい、とその太った体がゆすられる一瞬の出来事なのだ。見逃したら美はない。もちろん、カンテにも「渋」と「美」は各所にちりばめられている。カンテの美は、声が消えてゆく、その弱らせ方にこそある。大仰に言うとカンタオールの人生の味わいが出るのだ。技術的に巧みなだけで真実味のないカンタオールが、上手にやってのけても、心ある客は白けている。お世辞にも「オレ!」なんて言わない。 カンテは伝統的な形式を持っているので、美のあるべき箇所はおおむね決まっている。しかし、それをうまく踏襲しただけでは、やはり「オレ!」は出ない。何かその人でなければ出せない、新しい発見を示してくれなくてはダメだ。アタマや小手先でこさえた作り物の新しさではダメだ。昔、エンリケ・モレンテという人気カンタオールが、工夫してこさえたソレアの曲を歌った時、彼の故郷グラナダの観客は「フエラ(ひっこめ)!」と叫んで、実際に彼を引っ込めた。フラメンコの母といわれる古曲ソレアがアタマで蹂躙(じゅうりん)されるのに耐えられなかったのだ。 では、カンテの真実味とは何か? それは貧しいアンダルシアの、貧しい人々だけが持つ、真っすぐの生命力である。金持ちは、他人の分までを持っている人々である。こういう人が、なぜ魂の叫びを叫べるであろうか? 金持ちのキリスト、金持ちのゴッホが、いただろうか?マヌエル・アグへータの歌う古いカンテを聴くと、まさにそう語る声がきこえるのである。
[アート特派員]暗い目の美女に教わった極意(朝日新聞GLOVE)堀越千秋(画家)
僕はどぎまぎした。彼女の声は低いが、「赤を含んでいるな」と感じた。今風に言うと、これは逆ナンパされたということなのかもしれない。どこから来たのか、何をしているのか、などと彼女はたずね、スペイン初心者の僕は必死に答えた。 「絵を描いているの? じゃあ、このノートに私の顔を描いてみて」と彼女はほほ笑んだので、手持ちのボールペンで”しっかり”描いた。つまり、写実的に、彼女に似るように。「まかせとけ」という気持ちだった。出来たものを見せると、彼女は「これじゃあ、ただ見えるように描いただけだわ。もっとあなたの気持ちとか、心とかを描いて欲しかったの」と言って、つまらなそうな顔になり、「アディオス(さようなら)」と言って出て行ってしまった。あんなにガッカリしたことはない。 何が描写だ! 何がデッサンだ! 僕は、それまでの日本の画学生10年間の”修行”を呪った。しかし、振り返れば、ベラスケスもゴヤも、みな修行はデッサンではないか。呪われるようなものではあるまい。しかし、もう何だかよく分からないが、スペインに珍しい沈うつなムードの若い美しい女性が、僕のスケッチを見てつまらなそうに立ち去ってしまった、という事実は、1977年の若い僕を打ちのめした。 一本の線が、形が、人に何かを語りかけなければならないのだ。それが絵だ。美術学校のアトリエで身につけた技だけではダメなのだ。大事なのは「語る」ことだ。例えば、子供に向かって「ほおら、ゾウさんだぞぉ」と語りながら描くようなことだ。僕は彼女に語れなかったのだった。当時の僕の絵から現在の絵までを、今、東京で展示している。あの暗い目の美女に見せたら、今こそ何か言ってくれるかしら。彼女の身にも同じく35年が経っているわけだが。 http://globe.asahi.com/art_fashion/2012051700023.html [アート特派員]カタツムリが逃げない大きな壺(朝日新聞GLOVE)堀越千秋@マドリード
「何で穴が開いてるの?」 「カタツムリを入れておくのさ」。食べるためだから、2匹や3匹じゃない。 「逃げないかな?」 「逃げない」。自信たっぷりだ。 「これはカタルーニャの壺だ。あっちのカタツムリはでかいんだよ」何とも、多様な国である。 スペインの道路工事とか野外の労働現場の脇には、たいてい白い素焼きの水飲み壺が置いてあるものだ。2?3リットルは入りそうで、右肩に水の注ぎ口、左肩に小さな飲み口がついている。真ん中には、大きくて頑丈な輪があって、これで壺を釣っておいたり、そこを持って水を飲んだりするのである。素焼きの肌が、中の水を微妙に蒸散するので、水は常に冷たくなっている。炎天下、筋肉に汗をかいた男がこれを掲げて水を飲む姿は、まさにスペイン田園の風物詩である。僕が好きなのは、アンダルシア地方の美しい町ロンダのおっさんが作る、茶色い土の器だ。外側は赤茶の土色で、内側だけに茶や白の釉薬(ゆうやく)がかかっている。皿やボウルなどの実用品だが、シンプルで美しい。使っていると、自然の古色がついてきて楽しい。 同じアンダルシアで、世界遺産にも登録されたウベダの伝統的な緑色の陶器もいい。実用品から装飾品に至るまで、多様なものがある。ベージュ色の肌に青い釉薬で、鳥や獣やらの面白い絵や文様を描いた陶器は、スペイン各地にある。スペイン語でザクロという意味のグラナダには、このザクロを描いたものがたくさんある。これらの陶器はおおむね低火度で焼いているので柔らかく、割れやすい。 その分、長く使っていると、端などが小さく割れたり釉薬がはげたりして、我々日本人から見ると、たまらない、わびた味わいとなるのだが、スペイン人はどう思うのだろう?セビージャあたりの骨董(こっとう)屋では、そんな大皿や鉢などにも、いい値がついているから、まんざらピカピカだけが良いと思っているわけでもなさそうである。渋好みはどこにでもいると見える。 http://globe.asahi.com/art_fashion/2013031500015.html [アート特派員]なぜスペインには天才芸術家が多いのだろう(朝日新聞GLOVE)堀越千秋(画家)
そのくせ、他人が本当に困ったり苦しんだりしていると、天使のように助けてくれたりもする。試しにスペインの道で寝転んでみたら分かる。「どうしました?」と声がかかるだろう。日本なら、親切な人が呼んでくれた警察官が取り締まりに現れる。欧米語で敬語があるのはスペイン語だけではあるまいか。つまり、自分勝手でありながら、他人に優しく、気配りと(けいけん)さがある。 これが芸術表現を支える大きな心のもとではないだろうか。一見矛盾しているようでもあるが、芸術というのは、相反する二者を一つの中に昇華する仕事なのである。よく言われる、細心さと大胆さ、複雑にしてシンプル、男性的にして女性的、聖と俗、などなど。 木工師が「木の心を聴く」だとか、染織家が「藍ガメのつぶやきと語り合う」などというような、モノと語る習慣は、スペインには少ない。せいぜい牛と語って闘牛をやるくらいだ。それが裏目に出たのが、絵画の修復である。僕はこのごろ、あの世界の宝庫プラド美術館に行かない。修復が稚拙だから、たくさんの名画が台無しになっているのだ。 絵の中のシャツの白さは、絵の具の生の白ではありえない。そんな初心者でも知る基本を無視して、ハンカチも白雲も、同じ白になるまで、プラドの修復家たちは洗浄してしまう。ベラスケスもゴヤもグレコも、犠牲者である。権威に弱いのは日本人だけじゃない。怒っているのは僕だけだ。プラドへ行ってご覧なさい。名画は裸です。もう、元には戻らない。 http://globe.asahi.com/art_fashion/2012031500014.html [アート特派員] アンダルシアに死す(朝日新聞GLOVE)堀越千秋(画家)
日本からは小島章司フラメンコ舞踊団の作品「ラ・セレスティーナ」が招待された。この15世紀の有名な悲喜劇は、ピカソもリトグラフの連作の題材にしている。貴公子とお姫様の恋の仲を取り持って金もうけをたくらむ魔性の老女セレスティーナを、73歳の小島が妖しく深く舞う。 僕ら「ヤマコ組」がその舞台美術を作るのである。「ヤマコ」とはつまり「山乞食(こじき)」で、群馬の山奥で馬に乗ったり、耕したり、お金と関わりを少なくして楽しく生きている若者たちのことだ。僕は愛情を込めてそう呼んでいる。今回は6人。ドン帳などの絵は、群馬の山の中で描いてすでに送ってある。 舞台につる十三夜の大きな月、噴水、門、村広場の屋台といったオブジェは、現地ですべて作らねばならぬ。10日以内に ! 不景気で廃業した古いバルを借りて作業をした。町内の人々が中をのぞいていく。 「へえ、日本人か。君らはフラメンコが好きだよなあ。なぜだい?」 「日本とスペインは、両腕を広げた端と端ぐらい遠い。でも、ふたつの手の形は、ほら、同じじゃないか」 「クラーロ ! (なるほど)」アンダルシアでは、お金よりもユーモアが大事なのでみな貧乏である。 120キロの荷を解いて、20メートル×10メートルの大幕を4枚、炎天下の荒野に運んで補修した。深紅の布に赤い絵の具を塗るうちに、なぜか無性に腹が立ってきた。赤という色は、人の心を理屈抜きに熱くかきたてる。日本の原発、増税、外交、役人。通りすがりのスペイン人にあれこれとまくし立てると、彼は言った。 「カメレオンは、赤地の上に置くと憤死するんだよ」 変幻自在のカメレオンも、実は赤には染まれないのだという。染まれぬ赤に悶絶(もんぜつ)するカメレオンさながらに、日本を思い出して遥(はる)かアンダルシアにて憤死 ! 小島舞踊団の演目は大成功。スタンディングオベーションで称賛された。
[アート特派員]目の前にあるものに食らいつく(朝日新聞GLOVE)堀越千秋(画家)
僕も若いころは、ニューヨークに行ったりして、「アーティスト」になりたいと憧れたが、どうやら皆、僕より賢いらしいと分かった。で、今は山の中で昼寝をしたり、アンダルシアでふらふら遊んだり。つまり、ナメクジみたいに内臓だけで生きている感じだ。もちろん絵を描く。肉体派というより、ハラワタ派かしら。 しかし、描くとは何か? あるいは、何を描くのか? 若い頃は大いに悩んだ。とにかく、目の前にあるものに食いつく気迫だけはあった。で、プラド美術館のヴァン・デル・ワイデンの有名な大作「十字架降架」を模写することにした。「西洋絵画」というものに体ごと食らいついてみたかった。科学的、技法的模写ではなく、相撲の相手としてのワイデンだったのだ。フランドル絵画特有の精密な諧調(かいちょう)が魅力だった。 スペインにいるのだからスペイン絵画を模写したらよさそうなものだが、それは観光客のお土産思想であろう。美に国境はない。心にまず響いたものが大事なのだ。模写の許可はすぐ下りた。ワイデンの絵のすぐ前に画架を立ててもらい、持参のキャンバスをのせ、さあ、このキリストの裸体の絶妙なトーン、そのハーモニー、色、形をとにかくまねて奏でてみたい、一緒に歌ってみたい、の一心であった。 なんという高揚だったろう!死んだキリストの顔や髪やイバラの冠を、また、額の汗や胸の血の滴を、その見事さと(けいけん)さに感嘆しながら、僕はうっとりしながら描いた。ある雨の日。入場者もいない静かな館内に、突然ピシッ! という音が響いた。びっくりしたが、ワイデンの絵板のつなぎ目が、湿気を吸ってきしんだのであった。絵が生きている、と思った。 http://globe.asahi.com/art_fashion/2012081700007.html [アート特派員]スペイン人は異次元がお好き 堀越千秋@マドリード スペインのインテリは日本の“ブト”が大好きである。舞踏のことだ。僕自身はインテリだが(?)、普段つき合っているのは町のあんちゃんたちである。ある時インテリたちの宴会に顔を出したら、彼らはしきりに“ブト”の話をしている。何回かスペインに来て公演をした「山海塾」は特に有名だ。話は自然に日本人である僕の方に向いてくる。「君もブトをやるのかい?」「やらないけど、アマガツは友達だよ」「えっ、本当かい!」一同がみな顔を輝かしてこちらを見た。 アマガツとは山海塾の主宰、天児牛大のことである。「ひゃー、君は彼の友達か!ちょっとさわらしてもらっていいかい?(笑)」実際に彼は僕の腕にさわった。労せずして僕は称賛されたわけである。それより何年か前、山海塾の諸氏が恐らく初めてスペインに来て、ラバピエス劇場で「金柑少年」というのをやった。マグロの尾を無数に打ち付けた板を背景に、生きたクジャクを舞台に放して、静かな、しかし、熱狂的な舞が進行していった。終わると、客はみな立ち上がって床を踏みならして喝采をした。 僕は日本人のよしみで勝手に打ち上げにまで押しかけた。そうして深夜、マドリードの暗い隅に息づいているフラメンコの穴蔵に、山海塾の諸氏を案内した。深夜のフラメンコ男女がさんざめくサロンに彼らが入っていき、空いたテーブルに座るまでの数秒間に、客たちは一瞬、あっけにとられ、沈黙し、やがて笑い声とともに拍手が起こった。客たちはインテリではない。 多くは南のアンダルシアから来た労働者諸氏である。彼らは見知らぬ“ブト”は見に行かないが、目の前に突然現れた異形の東洋人、しかも舞台での白化粧は落としているが、みなつるつる顔の不思議さに感銘を受けたのだろう。異形のまま、すましてスルスルとどんな所にでも入っていくというのは、舞台ならずとも、おどりそのものであろう。にしても、スペイン人は、こういう突然の異次元、異世界の挿入を、びっくりして排除するのではなく、むしろ面白がって迎え入れるという性質がある。 コロンブスのアメリカ大陸侵入以来、南米諸国は混血文化である。現地の人となじまず、長年のアパルトヘイトを敷いた英国人とは対照的である。長年スペインに住んでいると、これは偉大なことだなあ、としみじみ思うのである。そう、スペイン人は異次元が好き。ピカソのキュビズムの絵を思い起こしてほしい。左から見た鼻と右から見た目を同じ顔の中に描きこんでしまう。異次元を暗示しているというより、ピカソの異次元好きの深さを、僕は見るのだ。 先のボルハの町の教会の古画修復事件もまた異次元であった。古いキリスト像をお猿さんみたいに塗って得々としている画家の老女はもちろん異次元だが、いったんあぜんとした人々はすぐに笑い出し、拍手をした。町は有名になり、観光客で潤うようになった。 さて、日本人は? 「オリンピックの日本と、この放射能汚染の私らの村とは、別の国ですね」と、福島の被災者が語るのをテレビで見た。日本人は異次元を見て見ぬふりをするのである。
|